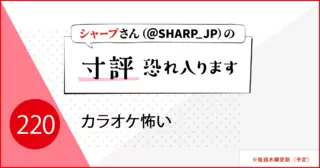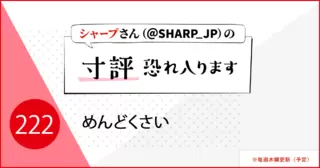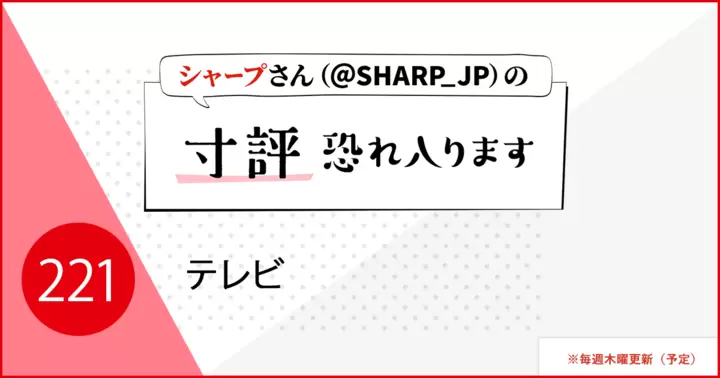
テレビとはすっかり疎遠になりました、@SHARP_JP です。職業が起きている間中ツイートすることだったり、名前にデジタルと付く場所や手法で広告を考える仕事をしているせいで、私はほぼずっとインターネットにいる。いまさらインターネットに入り浸るというのも、とりたてて珍しいことでもない。これをスマホで読むあなたも、インターネットやSNSに住んでいるといってもいい生活をしているのかもしれない。
とはいえ私は、仕事すらインターネット内で完結してしまうので、職住近接としてインターネットがある。そこで働き、暮らすうちに、もはや私にとって第二の世間ともいうべき場所が、いつしか強固に立ち上がってくる。私には暮らす世間がふたつあるのだ。
世間がふたつあるといっても、VR空間にこそ解放された本当の自分がいるとか、サブアカによって昼間とは別の顔を見せるといった、自己実現とか自己表現に関わる大それたものではない。私はただ、どちらの世間にも帰属意識が希薄で、どちらかの世間が言う「世間の常識」なる尺度を相対的に眺めてしまう、良いんだか悪いんだかわからない感覚をふわふわしている。
とても卑近な例を挙げよう。テレビである。テレビ番組のことではなく、それを映す機器のことだ。インターネット側の世間にいると、もはやだれの家にもテレビがないのでは、という常識に行き当たる。みなさんも心当たりがあるかもしれない。われわれはもう、テレビなんかいらない。スマホでじゅうぶんだ。誰もテレビを買う/選ぶことを話題にしない。そういう感覚が、インターネットでテレビを広告する私に躊躇を感じさせる。だれも欲しくない商品を推していったい何になるのだ、と。
しかしもう一方の世間を覗くと様相は異なる。テレビはあいかわらず、とは言えなくとも、粛々と売れているのだ。メーカーが一年間で売ったテレビの台数を眺めれば、われわれの家にはテレビがないとは決して思えない売り上げがそこにある。どちらが正しい、というわけではないのだろう。たぶん私たちの世間はそれぞれ、並行世界にあるのだ。テレビが生活のウェイトを下げ続ける世間と、テレビがあいかわらずリビングで発光し続ける世間。ふたつの世間が交差しない世界で、テレビは減りながら増えているのかもしれない。私はテレビのことを考えると、いつもよくわからない気持ちになる。
【くそじみLife 3/22】テレビない人のWBCの楽しみ方(karukoohino 著)
ただし、ごく稀にふたつの世間が重なる時がある。先日の野球の祭典は、その際たるものだ。どちらの世間でも、みんながテレビを見ていた。まるでお茶の間がフローリングの下からせり出してきたかのように、老若男女が同時に同じ画面を見つめていた。そういう感覚をひさしぶりに味わったような気がする。たしか2年前のスポーツの祭典でも、味わえなかった感覚だ。
とはいえ、現実にテレビを持たない人はいる。そのうちの多くの人は、このマンガのように、お茶の間から漏れ聞こえる空気の振動を耳でとらえたり、沸きおこる歓声をスマホ越しの文字としてキャッチしたのだろう。それは逆説的に、ふたつの世間が交差した証左でもある。
テレビを必要としない人は増えている。テレビを捨てた人が多数を占める世間も大きくなっている。テレビを製造する会社に勤める人間として、それは少し不安で、少し寂しいことではある。けれどテレビをみんなで固唾を飲んで見つめるカタルシスを知ると、まだまだテレビも捨てたもんじゃないよな、と思い直す程度には、私も現金な人間なのだ。みんな、テレビもう一度買わない?