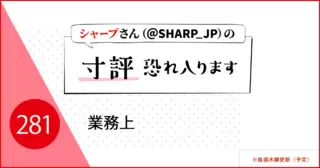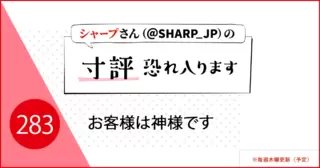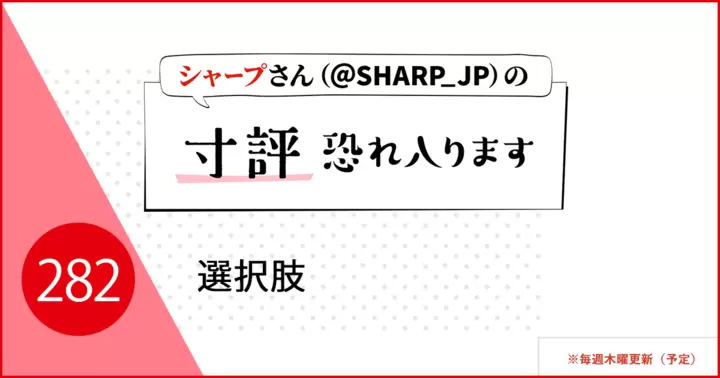
選んでますか、@SHARP_JP です。マーケティングとか行動経済学とか、なんかそういうモノを売る界隈でよく知られる定説に、ジャムの法則というのがある。たとえばスーパーの棚で、ジャムを24種類取り揃えた場合と6種類取り揃えた場合では、ジャムを買う人の率は6種類の方が圧倒的に多いという説だ。
ちなみに棚の前でまず試食をすすめると、24種類のジャムの方が試そうとする率は高かったので、買おうとする人ですら迷った末に購入そのものをやめがちなことを示している。人間は選択肢が多すぎると1つを選ぶのが難しくなり、検討すら放棄するから、モノを売りたいなら選択肢を増やすな、という法則である。
それを聞いた当初は「そんなもんかな」と納得しつつも、迷うくらいなら全部買っちゃえというお布施的消費もあるし、選ぶ過程がたのしい買い物だってあるよな、と思っていた。とりわけクオリティとかスペックを問われる、ガジェットとかマシンと呼ばれるような業界は、選択と吟味こそを楽しむお客さんに支えられてきたといってもいい。
現に私も、むやみやたらとカラバリを出すテレビや携帯電話の広告を考えたこともあるから、釈然としない気持ちになる時はある。逆に「なんで白や黒がないのか」と、せっかく買おうとしているお客さんから苦言を受けることもある。選択肢を増やすなと教えられながら、選択肢が多いことを讃歌するわけで、そこにはただ「どっちやねん」という矛盾がくすぶるばかりであった。
でも毎日ご飯を作るようになって私はわかった。家事の中でもしんどさがつきまとう料理に身を置いてみたら、そのしんどさの多くが「献立を決める」ことにあると実感したのだ。料理をするうちに、だんだん「きょうの晩ごはんを何にするかを決める」時間に、澱のような億劫さを感じるようになった。
選択肢が多かろうが少なかろうが、私たちはそもそも「決めること」がしんどいのではないか。スーパーを何周してもなぜかひとつも献立が思い浮かばない時。作ろうと思った料理が2日前と同じだと気づいた時。冷蔵庫の残りの食材が食べたい献立とは異なる圧力をかけてくる時。真綿で首をしめるようにレパートリーを狭めてくる1週間を繰り返すたび、取りうる選択肢を決める行為に嫌気がさす。その嫌気は、24種類が並ぶジャムの前にした時の気持ちにそうとう通ずるはずだと、いまならわかる。
ありえないバイト名鑑 献立決定代理(ヒバライ バイト 著)
だからこのマンガのように、献立を代わりに決めるバイトは案外多くのニーズに応えるのではないかと思えてくる。というより毎日SNSやネットのいたるところで、時短・かんたんを謳うレシピや、至高や虚無の文字が形容詞におどる料理を教えてくれる方々に、私も含めた膨大な人が救いを感じていることを見れば、献立決定代理というありえないバイトは、もうすでにありえているのかもしれない。
いま多くの信頼を得ている料理家やレシピ研究家と呼ばれる人は、料理の仕方を教えているのではなくて、私たちから選択肢を奪ってくれている。そう考えると、われわれの生活につきまとう「決めるしんどさ」を肩代わりしてくれるヒーローのように思えてこないだろうか。もはや私は、その日にSNSで見た料理を晩に作るのが、しんどくないルーティーンとして確立しつつある。決める行為は時に私たちを、じわじわ疲弊させていくのだ。