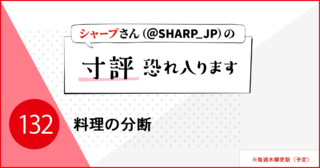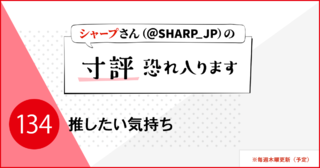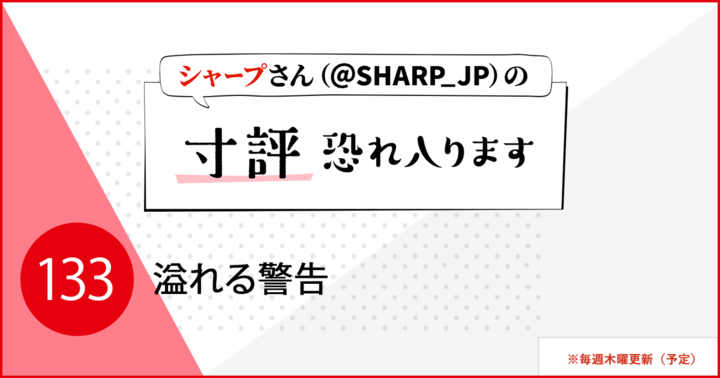
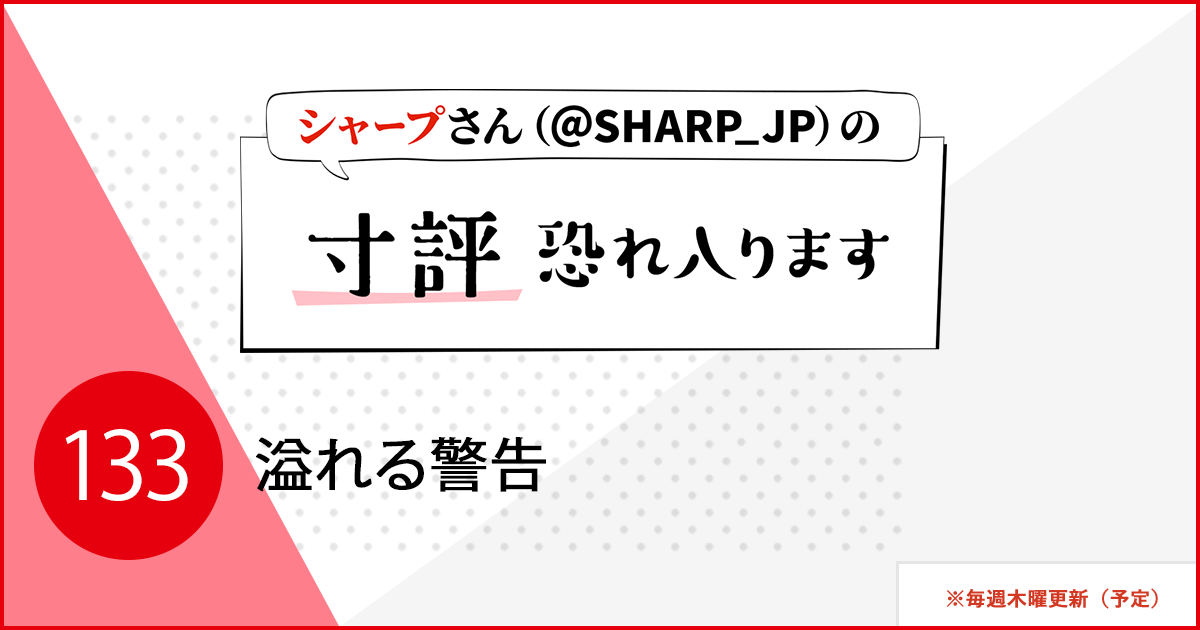
ぼんやりしてます、@SHARP_JP です。生きているといろいろと警告を受ける。止まらないと撃つぞほどの警告はさすがにないとしても「ほんとうにいいんですね?」「もう一度聞きますけどいいんですね?」といった警告なら、パソコンやスマホを触っている私たちにとって、日常茶飯事の警告だろう。
ゴミを捨てようとしたら「ゴミ箱に入れますか?」だし、アンケートに答えたら「送信しますか?」と念押しされる。勉強してテストに臨んだら「ほんとうにこれで採点していいの?」と不安にさせられ、自分の名前を打ち込もうものなら「個人情報だな?」といちいち再確認される。労働の疲れが色濃く浮いた顔でよろよろ缶ビールをさしだしても、最後の会計で「お前はほんとうに成人か」と問われる。こちとらベテランの成人である。見ればわかるだろう。
どれもこれも、やさしい顔をした警告だ。私たちのリスクを減ずるために必要なことだけど、繰り返されるとげんなりするし、慇懃無礼がどういうことか、だんだん身に沁みさえする。
一方、私は家電メーカーに勤める人間なので、しばしば警告を発する側にもなりうる。取説の冒頭は「やってはいけないこと」のオンパレードだし、カタログや広告では「条件付きの宣伝文句」であることに誤解なきよう、言い訳めいた警告を列記する。
われわれメーカーサイドは、絶対に必要なことだからと、粛々と微に入り細に穿つ警告で余白を埋めていく。かくして、読み飛ばされることを宿命づけられた悲しい取説やカタログが、連綿と作られ続けるのだ。
リサイクルショップ店員から1ページ!第6話(パンチコン 著)
警告はスルーされる。警告する側の目論見を超えて、華麗にスルーされる。たとえばこのマンガで描かれるようなケースだ。空気清浄機を買ったはいいものの、フィルターのビニールを取らないまま作動を続けているケースがまれにある。まれと言ったが、実はけっこうある。
まさかと思う人はまさかなのだが、まさかはひんぱんに起こる。だからメーカーは取説だけでなく「ビニールを取って」という注意喚起をA4紙で家電本体にでかでかと貼るのだけど、その警告はあえなく無に帰すことがある。そもそも人の認知とは、人の手でコントロールすることなどできないのかもしれない。
もちろんそういう人に対して「取説読め、ちゃんと見ろ」と冷たい警告で話を閉じる選択もあるだろう。ここから先はあなたの責任だ。私にもそういう気持ちがないわけではない。しかしもう少しだけ、ここまでしても警告が届かない人がいることを、考えたいのだ。
警告は飽和すると、警告の意味を失うのではないか。私たちの日常はいかに警告にあふれているか。わたしたちはどれほど警告を浴びてきたか。同じ内容の警告を壊れたロボットのように繰り返されてきたか。つまりは警告する側の「よかれ」が「うんざり」を引き起こしていないか。
私は「ビニールを取れ」と書かれた警告をスルーする人が経験してきた警告の数を想像する。そしてそのうちのいかほどが「取るに足らない警告であったか」を想像する。
警告を発する親切心が、警告を取るに足らないものにしてきた可能性。そしてその時の親切心が、実は使う人への不信と背中あわせだった可能性。もしそうだとしたら、警告する側とされる側、お互いの信用が築けていない関係性こそを危惧すべきなのかもしれない。相手がバカだからとひらがなやルビがふられ、極度に平易に書かれた文章を読まされる時、私はどう思うか。それと同じように、相手への信任を欠いた警告は、はたして届くだろうか。それが繰り返された先の警告は、もはや取るに足らないものだろう。
そこまで考えると、取るに足らない警告は政治への不信や社会インフラへの不安と地続きな気がしてきて、私はふたたび空恐ろしい気持ちになるのだ。