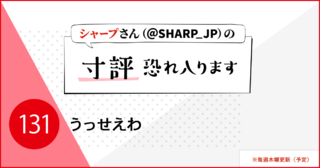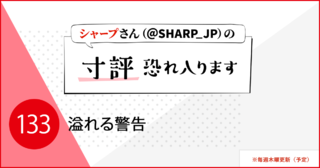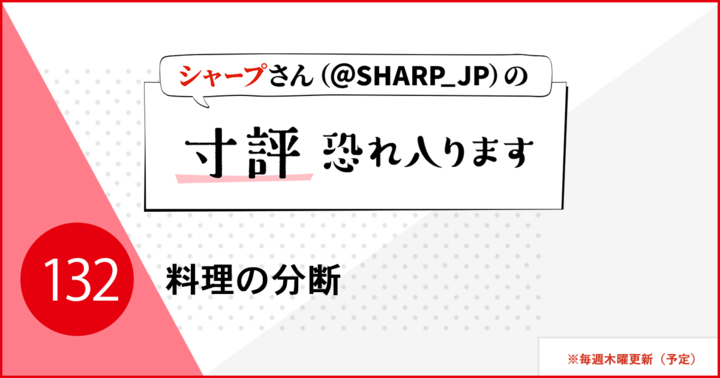
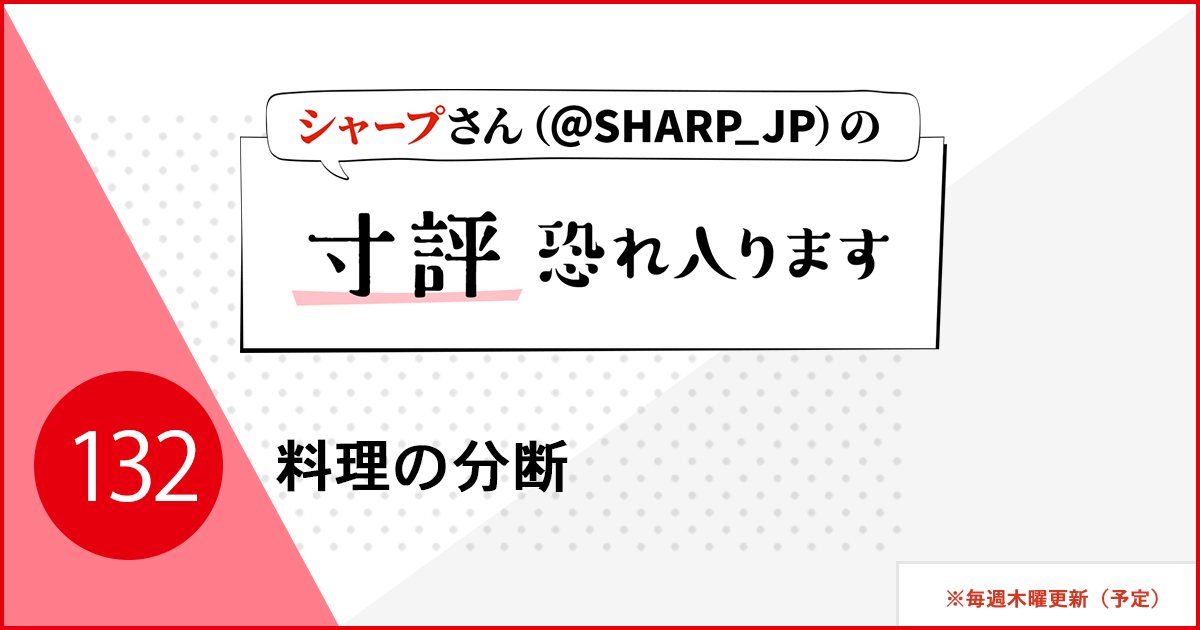
作るメシが茶色になりがち、@SHARP_JP です。私は料理をする。どちらかというと好きだ。得意な方だとさえ思っている。ただし人前で「料理が得意」と言うのは、慎重になった方がいい。私は、自炊と呼ぶにふさわしい、あるものでなんとかする料理が得意なのだが、しばしば豪勢で凝った料理を作るのがうまいと解釈されることがある。人により、料理と聞いてイメージする料理がちがうのだろう。
つまりは「料理をする」の「する」が厄介なのだ。料理を必要に迫られてするのか、娯楽としてするのか。自分のために料理をするのか、だれかのためにするのか。食欲を満たすために料理をするのか、生活を映えさせるためにするのか。料理をするの「する」には、真逆のベクトルをもった目的と行為が含まれている。
一方で、料理への向きあい方もそれぞれだ。効率やコスパを追求する人もいれば、じっくり時間と労力をかける人もいる。料理をタスクと称する人もいれば、愛情と表現する人もいる。料理が家事に組み込まれているのか、趣味に投じられているのか、それによって料理への態度も変わってくるだろう。くわえて、家事にコミットする人から見る食卓と、家事に無縁な人が見る食卓では、たとえ同じ料理が並んでいても、その景色はまったく異なるものとして映るにちがいない。
おそらくいま私たちの社会では、料理を挟んで分断が進行している。料理は効率よくこなすもの、料理はていねいに暮らすもの。どちらに立脚するかで、刻々と料理をする人の分断が進む。さらに料理をしない人の間でも、料理はだれがするべきか、料理はだれのためにあるのか、食卓に投影する願望や価値観は現実と乖離する一方である。だからこそ冷凍餃子やポテサラ論争といった、不寛容な衝突が巻き起こるのだろう。
その分断を象徴するかのように、調理家電の広告にはたいてい「ていねいにじっくり」と「楽にはやく」の宣伝文句が、おいしさのスペックに同居する。どちらにもする目配せは、どちらにも振り向いてもらえないのが世の常だから、その広告も虚しくスルーされることが多い。そこをなんとかするのが私の仕事でもあるのだが、分断は思いの外に根深くて、なかなかに難しいのだ。
「料理」を楽しむにはどうしたらいいの?(にいろはるをみ著)
いささか不純な理由で、作者が料理に本腰を入れようとするマンガ。料理は空腹を満たすための「作業」としてとらえてきた作者は、料理をテーマにした名作マンガにはことごとく、料理を楽しむ様が描かれていることに気づく。タスクか、楽しみか。まさに料理の分断を越えようとする作者の模索が、これから描かれていくのだろう。
私はどちらかというと料理はタスクと捉えるタイプだ。やらないと終わらないからやるし、楽しさよりも効率を重視する傾向があると思う。しかし一方で、そこそこ料理に向きあってきた私は、タスクの中に楽しさを見出せることもまた知っている。
料理は重ねると、自分を知ることになる。たとえどんなに簡素な料理でも、見よう見まねをすることで、自分の好みが浮かび上がってくる。好きな味や素材。はやくてうまい。じっくりでうまい。少しをたくさん。ひとつをたくさん。自分が作った料理には、自分はいったいなにが好きで、なにを大事に思うのか、じぶんのかけらが後味のように残るのだ。
自分を知ることは、いつだって新鮮で、そして楽しい。料理をしない人は一度、自分のために料理をしてみればいい。料理を巡って価値観の衝突が起こる時代に、それは分断を乗り越える、数少ない手段のひとつではないか。作り慣れた茶色くて名前のつかない料理を食べるたび、私はそう思うのである。