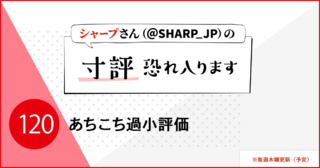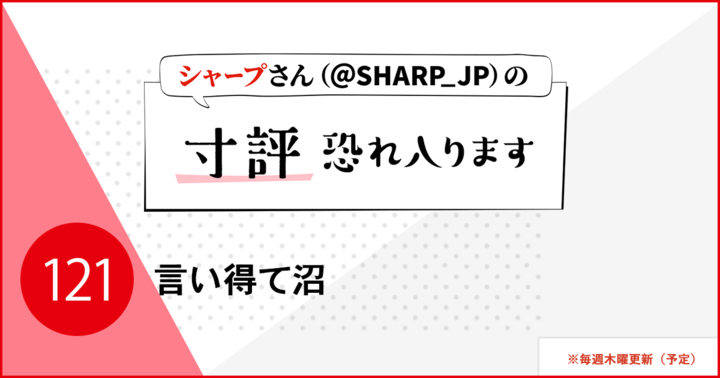
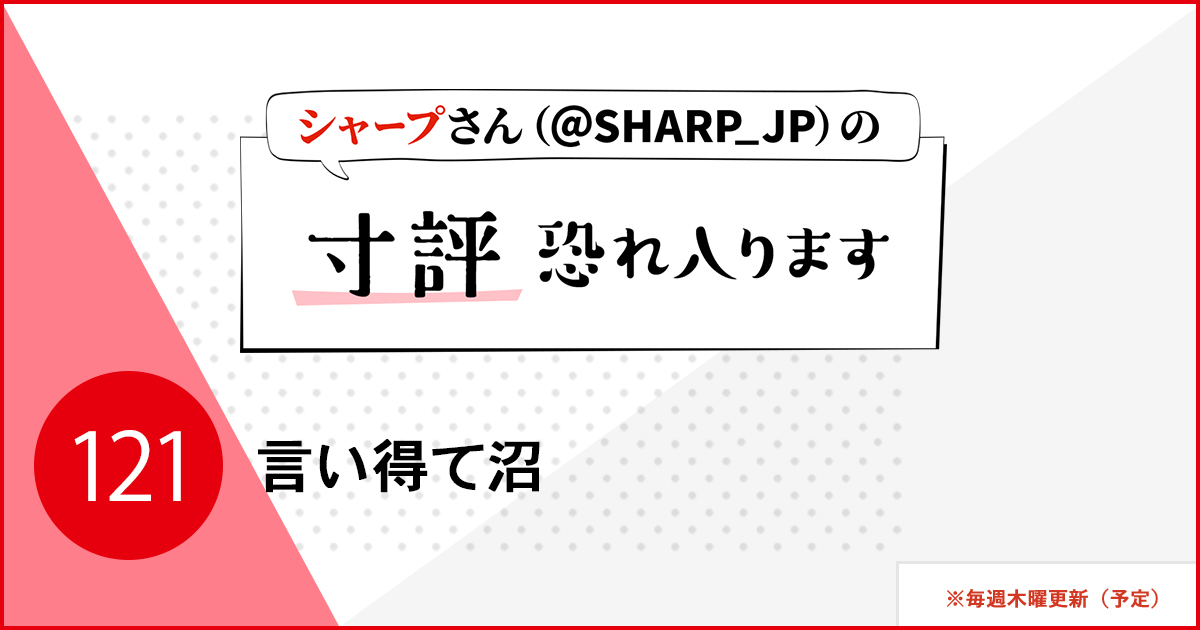
抜け出せないものはありますか、@SHARP_JPです。はじめて聞いた時、言い得て妙だな、と感心してしまう言葉がある。以前からそれはあったのに、それを的確に表する言葉がなかったために、広く知られることがなかった事象。あるいはその言葉が生まれたことで、無自覚だった行為が急に自覚されるような現象。それは医学の研究が進み、ある症状に病名がつけられた時に似ている。
たとえば「沼」だ。その言葉が生まれたことで、主に消費の場において「はまると抜け出せない世界」があることが広く知られるようになった。門外漢からは「どっちでもいっしょだろう」と思うような、微細な差異にこだわったモノを買い揃える行為を、沼と呼ぶ。おそらく沼という言葉が生まれる前は、集めることを目的とするコレクターといっしょくたにされつつ、当の本人も大雑把にマニアなどと称していたのではないか。沼という言葉によって、人は道具へ情熱とお金を注ぐという大義名分を自覚するようになったのかもしれない。
沼という言葉がよく使われるようになったのはいつからだろう。少なくとも、推しなどというワードが使われるよりずっと前のことだと思う(そういえば推しもはじめて聞いた時、言い得て妙だと唸った)
たしか私がはじめて沼という言葉に触れたのは、オーディオ沼とかレンズ沼と名付けられた沼だった。職業柄だろう。その言葉によって、ジャンル世界の深みを感じさせるのはもちろん、素人には識別不能なスペックを追究して抜け出せなくなる、消費の奥地があることが一瞬で理解できた。それはマニアックとかブランドとかいう、マーケティング的な形容詞よりずっと短くて、解像度の高い言葉だった。
沼は、作り手や売り手にとっても機能する言葉だ。分かる人にだけ分かればいいと、思う存分にモノやコトにこだわる大義名分は、なにも消費する側だけのものではないだろう。存分なこだわりを注げるだけ注いでよい場所があるという自覚は、時にメーカーやお店を励ますはずだ。沼とは、需要と供給が共犯関係を結ぶ場所なのかもしれない。作る側と買う側がズブズブの関係になれるのだから、沼が底なしになるのも頷ける。
コンプレックスからはじまった私の沼の話(いくたはな 著)
そしてこれは万年筆沼の話である。人が沼にはまる様子が克明に描かれている。当たり前だが、文房具は道具だ。コレクション以前に、使うという行為がある。字が汚いというコンプレックスがあった作者にとって、道具のおかげで字を書くのが楽しくなった経験は、そうとう強烈だったのだろう。
もちろん道具はプロダクトだから、道具を研究し、工夫をこらして製造する作り手が存在する。作り手と受け手が出会い、存分なこだわりを交換できれば、そこはもう立派な沼だ。ましてや万年筆である。歴史と特別が両立するモノに、インクという色が掛け合わされるのだから、その沼の深さは推して知るべしだろう。
書きながら私の沼はなにかと考えていた。かろうじて私が沼と言えるのは、ニューバランスのスニーカーだろうか。沼の深みはまだまだ知る由はないし、沼に両足を踏み込んだ覚えもないけれど、私の靴棚には990番台の数字がついたスニーカーが並んでいる。自分が怖い。