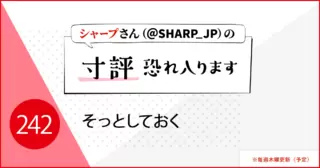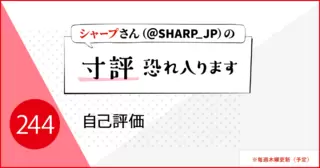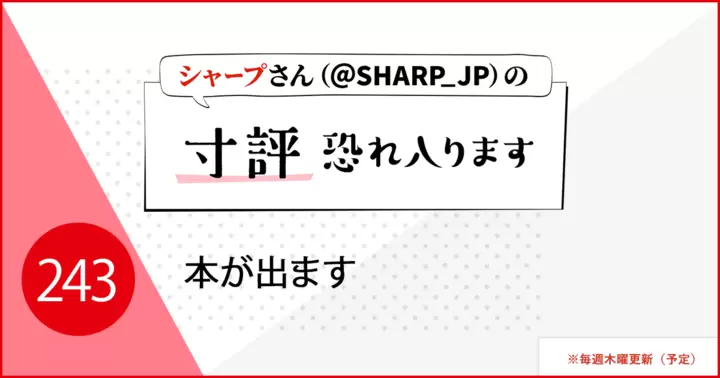
243回目のこんにちは、@SHARP_JP です。長く続けていると思いがけずいいことがあるということは、コツコツと創作を続けるマンガ家さんの中に、頷いてくれる人もいるだろう。とても光栄なことに、ここでコツコツと続けてきた連載がとりあげたマンガも丸ごと込みで、書籍にしてもらえることになった。そしてその本が、明日いよいよ発売になる。面映ゆい気持ちだが、率直に言って、とてもうれしい。
月並みな表現で申し訳ないけど、連載が書籍になったのは、いつもここを読んでくれる読者の方々と、ここで創作を公開するマンガ家さんのおかげだ。だから感謝を申し上げたいと思うのだが、その感謝をこめて書いたのが、書籍の最後に収録された「あとがき」なのだった。なので、そのあとがきをここに転載しようと思う。もしかしたら出版社の人は怒るかもしれないけど、感謝は伝えるべき人に伝えるのが筋だろう。
以下が書籍に収録されたあとがきである。なぜこの連載がはじまったのかも含めて、経緯も書いた。いつものコラムに比べて文量があるけど、よかったら読んでほしい。そして書籍も買ってほしい。つまりはそういうことである。
---
〈あとがき〉
まさか自分の人生に、あとがきを書く時が訪れるとは想像もしなかった。私も少なからず本に救われてきた人間だ。自分の文章が本になるという現実に、ふつふつと喜びがこみ上げてくる。しかしこれらのコラムは、もともと書籍化を目的にしていたわけではない。きっかけはただの仕事の、ひとつのアイデアだった。それは、なんでただの会社員が他人様のマンガをとりあげ、あれこれ語るようになったのか、という経緯でもある。
繰り返すが、私は会社や製品の宣伝をSNS上で行なうのが仕事だ。しかし本来の仕事は早々に霧散してしまった。なぜなら本来の仕事である宣伝や広告あるいは広報は、今の時代、容易に成立しないからだ。とりわけSNSでは、だれも会社の言い分なんて、目も耳も傾けてくれない。友人知人や推しの動向を見守る場所に現れる、縁もゆかりもない企業ほど、場違いな存在もないだろう。無遠慮にスマホの画面を占有する広告に、だれもがうんざりした経験もあると思う。とおり一遍の企業アカウントなんて、見る義理も読む義理もないのだ。
だから私はさっさと仕事を放棄した。広告を諦めたと言ってもいい。よくそんなことが許されたなとも思うが、当時の会社を取り巻く状況がシビアすぎて、それどころじゃなかったのが現実だろう。褒められたこともなかったし、むしろ怒られたことはあったが、自分なりの試行錯誤を、何度も何度もSNS上で行うことができた。その点はけっこう、会社に感謝している。
なにを試行錯誤していたかというと、広告せずに広告は可能かということと、企業はだれかの友人や推しになれるのか、ということである。私はおもに言葉を通して、その実現を目指していた。今も、それを目指して言葉を紡いでいる。その試行錯誤のひとつの結実がコラムだというと、ほとんどの人は「なにを言ってるんだコイツ」と思うだろう。自社製品がなにも出てこない文章である。ただし私が結実を訴えたいのは「マンガの力」だ。
言うまでもなく、マンガはすごい。スルーが当たり前のSNSで、マンガだけは読まれるのだ。私がいくら言葉を尽くそうが、わかりやすい動画を作ろうが、だれも見ない。しかしマンガなら無視されず、スルスルと読まれてしまう。バズったと呼ばれるモノの中に、いかにマンガを使った表現が多いかという点でも、その伝わりやすさの力がわかるだろう。そんな事例の数々を私は目撃してきた。だから広告を諦めた私は、マンガに頼ろうと考えたのだ。
そこで相談を持ちかけたのがコミチという場所だった。さまざまな漫画家が創作と試行を公開するコミチで、私は伝わらない広告を伝わるように変換してもらおうとしたのである。そして実施したのが「だれも読まない家電の取説をマンガにする」コンテストだった。その受賞作に私がひとつずつ選評を書いたのが、この本に収録されたコラムの原型である。
その選評を書くのが、意外にも楽しい仕事だった。あまりに楽しかったので、今度は私がマンガという表現を推したいと考えてしまった。そうやって応援していれば、マンガの中で自社製品を描いてくれる漫画家も増えるのではという、遠回りな打算もあった。私が広告しなくとも、だれかのマンガに製品が登場するようになれば、広告せずに広告するが成立するのではないかと目論んだのだ。
その目論見が達成したのか、実際のところはわからない。しかし毎回、私はマンガの「伝わる力」に舌を巻きながらコラムを書いていた。事実、この本にあるマンガのいくつかは、マンガだけで大きなバズを生んでいる。私はバズという言葉にためらいや意味の不足を覚える人間だが、多くの人に伝わり、感情を喚起した結果をバズは示す。伝える・伝わるが困難な時代に、マンガという表現手段は最後の希望ではと、広告を諦めた私は切に感じている。
ところでふだんの私は、書く文章の単位が小さい。SNSを仕事場にしていると、言葉は短く、テキストは細切れになる。文章は練り上げるよりも、応答速度を重視してしまう。それはコミュニケーションのスピードが加速することを宿命づけられた時代の職業病とも言えるだろう。その速度に疲れたというか、飽きたというか、言葉と会話にうっすら倦むような気分を、スマホを手に、持て余している人もいると思う。
私も連載をはじめた当初、もう少しまとまった分量の文章を書きたい、と思っていた。もう少しゆっくり、じっくり読んでもらえるような場所が欲しかったのだ。いざ連載がはじまると締切は飛ぶように過ぎ、まったくもってじっくり書くことはなかったが、メディアの制約もなく、「長く書いてもよい」のはうれしかった。そして「長くても読んでもらえる安心感」は、せわしないコミュニケーションを課せられた私にとって、なんともありがたかった。そんな穏やかな場所が、長く続けられた要因だと思う。その場所を作ってくれたのはコミチのみなさん、そこで投稿される漫画家さん、そして毎週じっくり読んでくださる読者のおかげだと、今更ながらに思います。ありがとうございます。
そこで書き続けたコラムが、私の意図を遥かに飛び越え、書籍になりました。コミチの萬田さん、荒井さん、作品の収録に快諾くださった漫画家のみなさん、それから「これを書籍にしましょう」と気長に、ほんとうに気長におつきあいくださった編集の寺崎さん、ありがとうございました。このあとに続く解説を書いてくれたロザン宇治原さんも、古い友人の無茶振りにつきあってくれてありがとう。そしてなにより、スマホを脇にそっと置き、ここまで読んでくださったみなさまに感謝します。
広告を諦める代わりに勇気を出した10年前の私に、「こんないいことがあるぞ」と本を差し出したい。いま、そういう気持ちです。