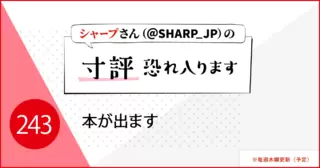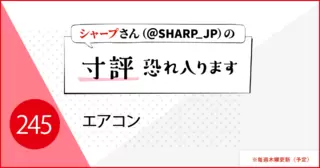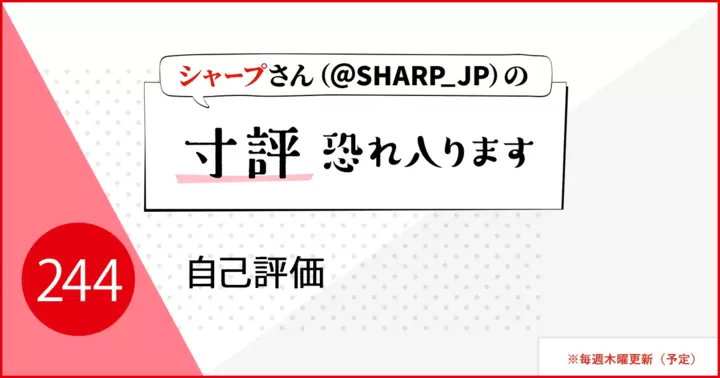
可もなく不可もなく、@SHARP_JP です。むかしから自己アピールや自薦が苦手だ。自分が正当に評価されるため、まず自分で自分の評価を測定し、その妥当性を主張する行為に、どうにも欺瞞や気恥ずかしさがつきまうのである。なにが言いたいかというと、どこの会社でも繰り広げられているであろう、今期の私の業績を自己評価として上司にアピールしたり面談したりする、査定前のあの風習がどうにも苦手なのだ。
学校にいる頃は、テスト前に自分がいかに勉強したかをアピールする機会などなく、ただただ点数のみが評価となる仕組みが過酷だったけれど、評価前に自己PRが与えられた大人の私は、あの頃のシンプルさにあこがれさえ感じている。他人に向かって自分を褒めたり、場合によっては自分を盛ることが、私は億劫で仕方ない。
もちろん意義はわかっている。自分の労働や成果を不当に低く見積もられたり、見えない労働や努力を見えないまま終わらせることを防ぐために、評価される側が評価する側に前もって主張できる機会は必要だと思う。制度として圧倒的に正しい。ただし私は、心の中にどこかやっぱり「評価は他者から下され、遅れて到来するもの」という気持ちが拭えないのである。
みんながそうであるように、私の仕事もその結果があまりに抽象的で茫漠としている。客観的指標でもって評価せよと言われましても、その指標が見つからないのだ。「今期はアレを何台売りました」と言い切ることができれば話ははやいが、あいにく私の仕事は売れるものでもない。もし仮に売れたとしても、アレは私のおかげだと断言できる根拠がない。だいたい世界中のあらゆる「売れた」は、無数のだれかの仕事が連鎖したバタフライエフェクトなのだ。蝶の羽ばたきひとつを取り出して「アレはおれの功績だ」と主張する勇気が、私にはない。
ましてや、私がやっているのは成果が遅れてやってくる種類の仕事である。成果がやってこないことも茶飯事だ。私の仕事は自販機でジュースを買うように、今期の努力を投入すれば、今期の成果がゴロンと到来するわけではない。もちろんそうなればうれしいが、そもそもそうならなくてもいいと考えている。私の仕事は、のんびりしているのだ。
さらに私は、われわれの仕事の大半はそういうもんでは、と思っている。私たちはなんだかんだで「いつかよくなれ、なんとかなれ」と願いながら、目の前の仕事をこなしているのではないか。言葉を変えれば、成果なんて二の次で、私たちは働いている。だいたい、やる前に成果が見通せるほど、私たちは見晴らしのよい場所で働けるわけではないのだ。そうやって私たちは近眼的にあくせく働きながら、それでも案外、長い未来の間合いを持っているのではないか。
だから私は、四半期とか半期で自己評価を求められるめまぐるしさと疚しさに、いつも立ち尽くしてしまうのだ。
『1Pマンガ 』「フィードバック」(まるいがんも 著)
一方で自己評価の後、会社から通知される評価の結果に、私たちはうっすらと諦めが漂うことも知っている。たぶんそこには、会社と労働の本質的な問題が横たわっているのだろう。乱暴に言ってしまえば、社員ひとりひとりの働きの総和が会社の利益なら、会社からの評価は常に、私たちの実際の働きより下回るはずではないか。それぞれのパフォーマンスに100%の報酬を払えば利益は相殺されてしまうから、私たちはいつも、少しずつ過小評価される運命にあるのだろう。
そうやって私たちは、仕事の上澄みを会社からすくいあげられながら働く。言葉を濁さず言えば、私たちはピンハネされながら働く。もちろんそうじゃない会社はたくさんあるはずだけど、いつも会社の評価が自己評価より小さいのは、だれかのせいというより、むしろ労働の構造だと思う。
だからこのマンガにおける、評価への飄々とした態度はとてもリアリティがある。そして同じようにリアリティを感じる人は、現代にはそうとう多いのではないか。いまや「飄々とする」は、自分を査定してくる力に対する、ひとつの合理的ふるまいに思えてくるのだ。