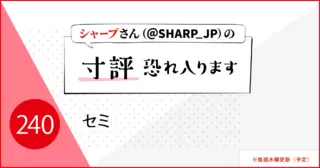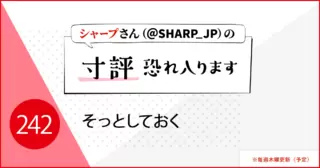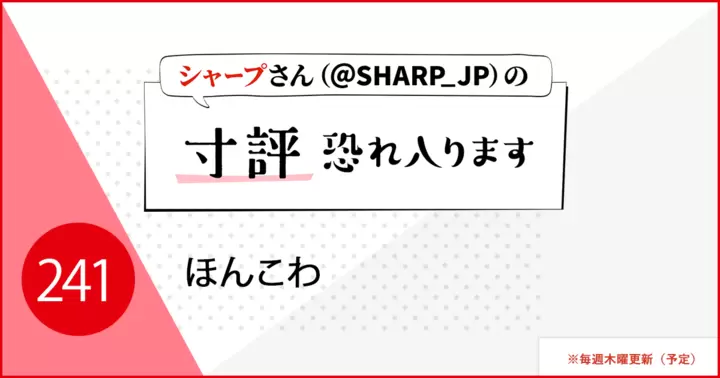
こわばりがちなこわがり、@SHARP_JP です。さいきんの猛暑は、怪談のニーズに変化をもたらしたのだろうか。夏休みのテレビが心霊番組と密接に結びついていた時代に育った私にとって、夏と得体の知れない怖さには、大人になってもうっすら相関関係がある。一方ただの体感だけど、アトラクション施設ではお化け屋敷を見かけなくなったし、肝試しというイベントも聞かなくなった。猛暑の夏は私たちを冷やりとさせるには暑すぎて、怪談や心霊を蒸発させてしまったのかもしれない。
もともと夏は盆という、死者をウェルカムで迎える催しがあるわけで、夏と心霊は親和性があったのだろう。盆踊りも当初は念仏と踊りのことで、踊っているうちにお盆の霊を送り返す行事と結びついたそうだ。びっくりさせるとか悲鳴を上げさせるといった意味での「こわい」は薄まったのかもしれないが、得体の知れないものへのまなざしは、いまだ夏が旺盛なのだと思う。私も記憶にある限り、根源的な怖さを感じるイメージにはじめて出会ったのも夏だった。
祖母の家はなかなかに大きく立派で、だから夏に訪れる私たちが寝泊まりするのは必要以上に大きな客間で、その和室にはおそらく高価であろう能面がふたつ飾ってあった。たしか、女性の面と鬼神の面だったと思う。夏の夜の幼い私は、天井近くの長押から見下ろす能面をどうにか視界に入れないように眠ろうとするけれど、寝苦しい夜はどうしても、見られているという確信が訪れてしまう。そこでいっそう怖さを喚起させるのは、決まってお歯黒の女面だった。せめてマシな方にと、私は鬼の方へ意識を向けようとするのだが、どうしてもうまくいかなくて、ひたすら怖かった。
あれはたぶん、なにをどうやっても話が通じなさそうな存在に恐怖していたのだと思う。鬼の方は幼心にも、怒ってるなと感情が理解できるのだ。しかし口と目を薄く開けた女面は、いったいなにを考えているのか、さっぱりわからない。そういう取りつく島もなさそうな存在が、幼い私にはどうにも受け入れられなかったのだ。いまでもやっぱり、なにか言いかけたまま停止したようで、それでいてまったくなにを言おうとしているのか皆目わからない能面を見るたび、根源的にこわいという感情がありありと立ち上がってくる。
本当にあった怖い話(Yoshuafocar1 著)
夏と怪談の関係は薄まったとはいえ、夏のインターネットではちらほら怖い話を見かける。怖さを語る季節のなごりがSNSにも染み出すように、あちこちで心霊体験が語られていたりする。このマンガもそのひとつだろう。そういえば学校という場所も、得体の知れない怖さをふりまくところだった。夜の学校なんて、ほとんどだれも足を踏み入れたことなどないのに。
そしてもうひとつ。夏のこわさの共通点は、上にあるということかもしれない。私が見下ろしてくる能面に恐怖したように、天井にペタペタつく足跡はさぞかし怖かったことだろう。
私は常にできる限り科学的であろうとする人間である。そうあらねばならぬという使命感のような決意もある。だから怪談や心霊の類には、いつも笑って対処しようとする。しかしその笑いの奥から、「なにを考えているのかさっぱりわからない」という得体の知れなさに、恐怖の根源を見出した子どもの私がひょっこり顔を出す時がある。夏の私はその目線に、いつもひやりとしてしまう。その事実が、ちょっとこわい。