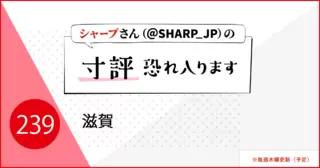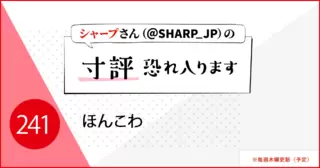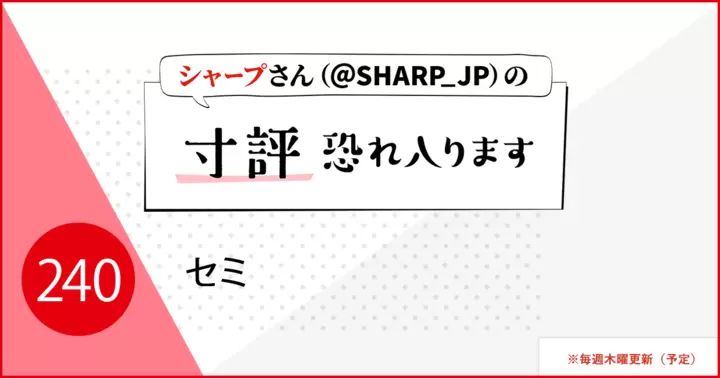
残暑お見舞い申し上げられたいです、@SHARP_JP です。猛暑と口にしようと口を開けば、その舌がもう暑いほどに毎日が暑いわけですが、みなさまいかがお過ごしですか。そろそろ猛暑と言うのも、飽きてきた。私たちはみな、うんざりしている。
セミは一定の気温以上になると鳴かないという知識はどこかで知っていて、たしかに早朝を過ぎると、ぴたりと鳴き止む。セミが鳴き止むころに、たいていのわれわれは労働をはじめ、ふたたびセミが鳴き始めるころ、たいていのわれわれは帰路につく。さいきんの夏はすっかり、セミと人間がシフト制を敷くようになった。
セミが一定の気温以上になると鳴かないのは、自分の身を守るためだからだそうで、そう考えるとセミが沈黙する時間に働くわれわれは、そうとう過酷な労働時間を毎日くぐり抜けているのかもしれない。たぶん人間より、セミの方が賢明なのだろう。
何年前の夏だったか忘れてしまったけれど、セミがいっせいに羽化する時間に遭遇したことがある。ふだんよく通る公園のいたるところで、いたるところという言い方では遥かに足りないくらいのあちこちで、あの茶色い殻からセミが半身を出し、自身がいた場所をもぬけの殻にしようとしていた。たしか時間は夜明け前とかそういう薄暗い時間ではなくて、もうすっかり日が昇り明るい時間だった。だからぐるりと見渡せば、セミがいっせいに羽化をはじめた様子が無数に、ありありと目についた。
羽化しようとするセミは驚くほど透明で、それでも同時に真っ白だった。同時多発羽化に出くわした私は白い発光体に囲まれて、白昼夢とはこんな感じかな、と考えていた。地中で数年、地上で数日の命とされるセミは、とかく薄幸な生き物として捉えてしまうから、羽化も感傷的に眺めてしまいそうなものだが、その時の私はそうではなかった。生命の神秘というより、光景の明度にびっくりしてしまって、しばらく立ち尽くしていた。あの時のセミは文字どおり、白く光っていた。透明なのに光っていたのだ。
課題/日記マンガ 第56話(園太 著)
このマンガで描かれるように、私たちは大人になるとなぜか、虫が苦手になる。私もそうだった。幼い頃は好きと興味が尽きない対象であったはずの虫が、青年期のブランクを挟み、苦手に変わってしまう。私もセミに行く手を塞がれると、なすすべがなかった。
ただセミの同時多発羽化に遭遇して以来、私はセミがさほど苦手ではなくなった。セミの羽化を白い発光として美しく経験した私は、とりわけクマゼミを見るたび、その透けた羽に発光の名残を見出す。それはいつだって一瞬だけど、とても静かで、生命を忘れる時間だ。もちろん静かな時間はじきに、セミの絶叫か、迸るおしっこで遮られる。そして私は、小さくひいぃと言いながら、手を振り払うのだ。