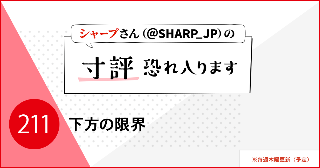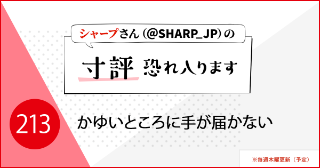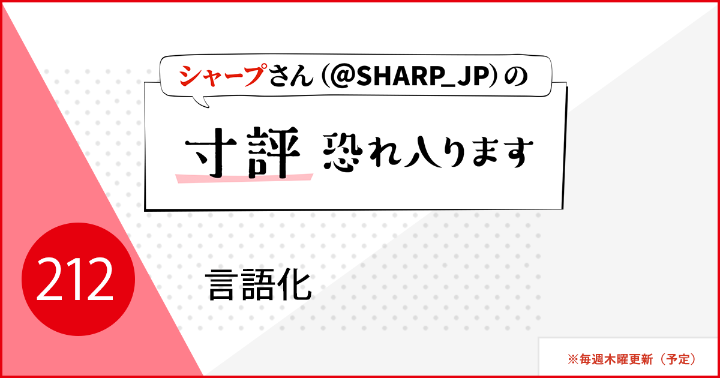
殴り書きの悪魔、@SHARP_JP です。仕事柄、言語化してくださいとか言語化がうまいですね、と言われる機会がある。たいていは、なんかうまいこと言ってくださいとかなんかうまいこと言ってますよねと同義なので、だいたいはあいまいな表情で聞き流すことにしている。さいきんは本屋でもネットでも「言語化がいかに大事か」というような意のタイトルを見かけるから、ビジネスや人生をうまくやるには、どうやら言語化が秘訣だとされているのだろう。
それを言語化と言っていいのかはわからないが、私の仕事は「限られた場所でなんか言って伝える」ことである。ツイッターなんて、その限られた場所の最たるものだろう。コトが製品の宣伝ともなると、あれもできるこれもできると機能を積み上げたスマホや、ここがちょっと便利でそこは少し使いやすくなりましたと改善を寄せ集めた冷蔵庫なんか、その全貌を限られた場所で説明するのは土台無理な話である。
だから私はまず、言わない機能をバッサバッサと捨てて行く。捨ておく機能にどれほど労力が注がれたか、どれほど社内の支持があるか、具体的な社員の顔が思い浮かぼうが未練はない。私の仕事は、伝わってほしい人に伝えることがすべてにおいての優先事項である。言わない選択をすることに、私は躊躇がない。
そうでなくとも広告なんて、伝わらないのだ。だれでも身に覚えがあると思うが、広告を見たってそれがどこのなんの広告か、一瞬たりとも覚えてなんかいられない。ただでさえ伝わらないなら、せめて「伝えるポイントはひとつに」とは、だれが考えてもわかる話だと思う。
つまり私は、言いたいことの中から「言わないこと」を無数に選択する。言えと言われていることでも、迷うことなく言わない。そうやって私は、言うを平気で伐採する。もし、伝える/伝わることが巷で話題にされる言語化の目的ならば、私は伝えるために、言語化しない部分を無慈悲に決めているのだろう。そうやって言語化すべきものごとを、ズカズカと軽くしているのだ。
人間11年生までのダイジェスト(多喜ざわゆき 著)
そもそも言語化とは、不思議な行為だ。いま盛んに語られる、マネジメントとかコミュニケーションの延長にある論とは別に、言語化には人間の内面を基盤から支える役割がある。自分の感情をどう把握し、自分の心象をどう表現するか、その営みの第一歩目になぜか「体系だった言語」が必要なことが、この体験マンガを読むとよくわかる。
心象を映像でそのまま受け渡すことができれば、おそらく自分の伝えたいことを過不足なく他者に伝えることはできるだろう。しかしそれを成し遂げた人はいまだかつてない。それができないから私たちは、自分の心象を言葉にして、相手に渡そうとする。幼い子どもが大人相手にいつももどかしそうにしているのは、自分の感情を手渡すための言語を持ちあわせていないからだろう。
しかし言語化とは同時に、本来の丸ごと伝えたいことを、言葉によって省略し抽象化し時間を圧縮することでもある。私たちは伝えるために伝えることを軽くし、ある程度の欠落を受け入れるのは、カメラで撮った4K映像を持て余して、ファイルを軽くしたり切り抜きにしたりキャプチャー画像にしたり、あげくテキストにまとめて送ることと、どこか似ている。
一方、自分の心象を言語化によって間引くことは、伝えるためだけが目的でないように思える。言語化は、自分の心を守ることにも使われているのではないか。自分の心象や記憶をあますことなく映像で記録していけば、早々に自分の容量が破綻するのは容易に想像できるだろう。言語化で整理できないまま、生きる上での心象を抱え続けるしんどさもまた、このマンガで描かれているとおりだ。
ではなぜ人は言語化によって簡潔に心象や記憶を他者に伝えられるのに、わざわざフィクションや創作を交えて、物語や小説、マンガといった迂回する言語化を行うのだろう、という疑問もまた湧いてこないだろうか。それは人間のさらなる不思議な行為だと思うのだが、私にはまだそこを言語化できなさそうで、いつもぼんやり考えている。たぶんじっくり伝えるとか長く伝えるといったことが関わってそうだけど、これはまた別の機会に。