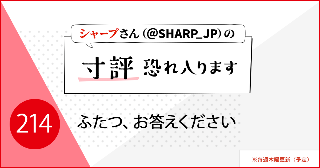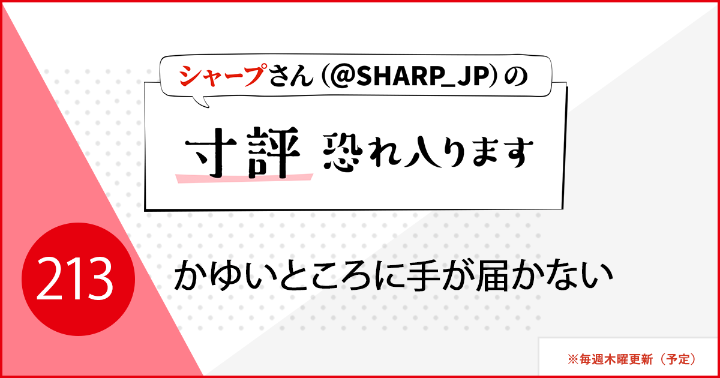
帯に短く襷にも短い、@SHARP_JP です。ものごとには一長一短がある。だからほどほどの妥協が肝心である。そういう風によく言われる。特に同じような製品がひしめきあうような、購入の選択肢が多いモノの場合、一長一短は買おうとする人にしばしば訪れる現象だろう。ちなみに2番目に多いのは「どれも同じやろ」である。
広義の意味でモノをおすすめしたり購入を促す、私のような人間がこういうことを言うと語弊があると思うが、買う前にモノの一長一短を把握することはけっこう難しい。とりわけ一短を見極めてから買うのは至難の技だ。
なぜなら一長は売る側がさかんに喧伝するから嫌でも目に入る一方、一短の方はわざわざ声を大にされることはない。広告には短所を記すスペースも時間もないし、忙しい接客では短所を説明する余裕もないだろう。買い物に限らず、私は相手に一短を等身大に開示することは、売り手や作り手、あるいはその人自身に信頼をもたらすと思っているが、まだまだ「アピールの場所でデメリットを語ることになんのメリットがあるのか」と考える人が大半だと思う。
さらに言えば一長一短の一短には、使ってはじめて認識される種類のものがある。長と短は対になって存在するが、短はたいてい遅れてやってくるのだ。部屋のクローゼットを開ければ、私たちは幾度となく「買ったけど、なんかちょっと違った」という経験を繰り返していることがわかるだろう。
そして、ちょっと違うとか、なんか足りないといった、事後的にやってくる短所は、その人の事情にフィットするかしないかに依存する。口コミやレビューを見ても、あくまで「個人の意見です」というかたちでしか表明できない短所は、そもそも作り手や売り手があらかじめ把握できない場所にあって、買う前に一長一短の偏差をなくすことをいっそう難しくしているのかもしれない。
#振り返りマンガ(shirokoueda 著)
繰り返すが、一長一短の一短はむずかしい問題である。短を知る機会は限られるし、作る方も使う方も、そもそもどこが短であるかをあらかじめ把握できない。人間の教育も多少の短所には目をつぶり、長所をどんどん伸ばしましょうという風潮にあるくらいだから、短の対処には労力と困難がつきまとうのだろう。
たぶん100均の人も、スクールぞうきんに輪っかになったひもを付けた時、完璧だと思ったはずなのだ。それなりのリサーチや勘定の上で、これでよかろうと輪っかのサイズを決め、一長ができたぞとガッツボーズで量産したはずだ。しかしその一長がちょっと短かったことは、このマンガを読めばわかるとおり。おそらくマンガの作者も、買ってからその一長が一短だったことに気づいたのだと思う。
私も日々、そういうちょっとした短の指摘を浴びる。カジュアルに声をかけてもらえるように努めるのが信条ゆえ、買ったけどここがちょっと、という意見がお客さんから押し寄せるのも宿命だと思っている。あとほんの数センチ低かったら。あのボタンさえ別の場所にあったら。コードがあと少しだけ長かったら。もうちょっと安かったら。かくして私のもとには「かゆいところに手が届かない」が吹き溜まり、私は「申し訳ありません」とぶつぶつ呟くことになる。
だから私は、できるだけ一長一短の両方を、買う前の段階から開示したい。それは「使ったらなんか違った」という作る側の不幸を未然に防ぐためでもあり、買う前に使う側が短所を認識するきっかけにもなるからだ。そしてなにより私は、一長一短の納得ずくで買った買い物にこそ、この人から買ってよかったというボーナスが発生すると信じているのだ。