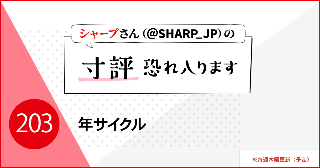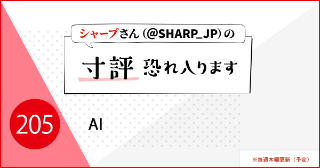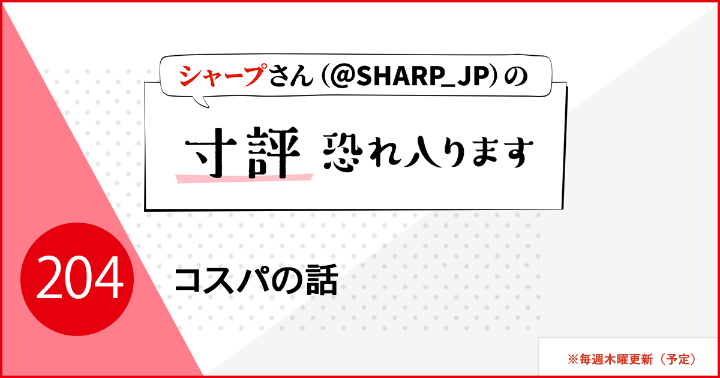
松竹梅があったら竹に手を伸ばしてしまう自分に、ときどき嫌気が差す。@SHARP_JP です。世の中には同じモノなのに値段に高低がある。食料品なら産地や鮮度によって値段がちがう。なんとなくだけど、豚肉や野菜は値段の差と質が必ずしも一致しないことがある一方、牛肉や魚は値段と質がきれいに比例しているような気がする。お金を払えば払うほど、おいしい。それは世知辛いけど、納得づくの世界だ。
家電にも同じく値段の高低がある。同じ画面サイズのテレビでも、あからさまに松竹梅な序列があるし、同じ容量の冷蔵庫や洗濯機なんかも、値段の階層がある。もちろん家電の値段の違いには、それなりの根拠が存在する。機能の多少や性能の大小がその根拠だ。テレビなら値段の高いモデルはより美しく映るし、冷蔵庫や洗濯機なら電気代の違いや使い勝手の違いがある。だから作り手は堂々と「これはお高いのです」と自称するのだ。
そして作る側や売る側は、できれば高い方を買ってほしい。自信があるから。さらに根も葉もないことまで言えば、松や竹を買う選択をしてもらうために、あえて梅を用意する、なんてこともある。そこそこいいものを選びたいという人間の心理を突くためだ。そして再びなんとなくだけど、少し前までその策はいわゆるマーケティング的な仕掛けとしてうまく機能していた。ほんの最近まで「メーカーがそこまで言うならそうなんだろう」と納得して、多くの人が松や竹を選んでくれていた気がするのだ。
それがいつしか様変わりしてしまった。コスパという言葉が定着した頃だろうか。払ったお金に見合う以上の機能や質を備えたモノこそ、買うべきモノと認識されるようになったのだろう。つまりはおねだん以上、が当たり前になったのだ。あるいは逆もあるかもしれない。手に入れるべき機能や質を固定して、いかに払うお金を少なくするかを評価する向きもある。コストを下げれば、パフォーマンスは相対的に上がる。自分の買い物を振り返っても、とにかくコスパが第一な時代になったと思う。
その変化は、私たちが「どれを買ってもそこそこいい」という買い物を経験してきた結果なのだろう。それは作る側の努力の結果とも言える。しかし同時にコスパのパを、作る側から買う側の手に渡すことにもなったのではないか。パの主導権が移動したのだ。モノのパフォーマンスを評価するのは買う人に委ねられ、パフォーマンスをプレゼンする機会も効力も、もはや作ったり売ったりする側にほとんどなくなってしまった。少し前からそういう無力感が私の中にある。
回らない寿司を食べに行きました(コジママユコ 著)
思えばずっと昔から「おねだん以上」に対峙してきたのは、飲食店の人たちなのかもしれない。外食のコスパなんて、お金を払って食べておいしいかがすべてなのだから、パの主導権はもとよりお客さん側にある。
一方、寿司なんて、まさに値段の高低がある食べ物の極地だ。なんでもそこそこおいしい時代に、値段が平準化せず、その高低がいまだに根強いのは、多くの人が「高いには理由がある」と納得しているからだろう。たとえお金を持っていてもしばし緊張を強いられる、あの回らないカウンターには、コスパのパの主導権は安易に渡さないぞという、お寿司屋さんの意思が現れているのかもしれない。
マンガを読み、そんなことを考えていると、寿司が食べたくなる。私は寿司が食べたい。願わくばだれかに奢ってもらって、寿司が食べたい。払うコストを限りなくゼロにすれば、パフォーマンスは無限大に向かう。コスパを最大化する秘訣は「人の金で」なのだろう。