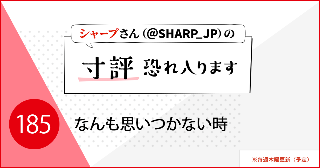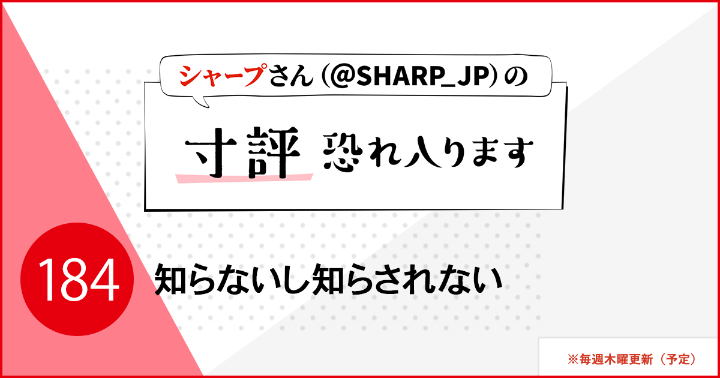
社会の構成員、@SHARP_JP です。この手の話に時効があるのかわからないが、会社が潰れかかった時の話をしようと思う。こう書くとまるで私が会社を経営していたように見えるけど、そうではない。私が雇われていた会社の話で、今も雇われている会社の話である。
7年前私が勤める会社は、一般に言うところの経営危機に陥った。「あのメーカー、潰れそうだぞ」と見られる状態である。歴史も長く、また家電というモノの性質上、日常生活で比較的多くの人に馴染みある会社だったせいか、そのピンチは広く世間から注目を集めた。
世間からの注目といっても、有名人の間を日替わりで渡り歩くゴシップとは異なり、瞬間風速的に耳目を集めるというよりかは、推移を見守るとでもいうような、一挙手一投足をじとっと注視される、独特の息苦しさがあった。経営の危機というものにはさまざまな段階があり、段階ごとの対処法や救出法もさまざまだから、世間の注目が長引くのも無理はない。当時の社員なら、友人と会うたびに同じ質問をされるとか、盆と正月に会う親戚から盆も正月も心配されるといったことがあったと思う。
世間の注目に独特の息苦しさがあったと感じる私には、すこし別の事情もあった。私は自分の働く会社が経営危機にある間中、ずっと会社のツイッターを担当していたからだ。エゴサをすれば、多くの人が家電以外の話題で会社の名を挙げていた時期である。その頃の私は、毎朝腹をくくるのが日課だった。いまで言うモーニングルーティーンか。7年前の私は、朝起きて、顔を洗い、コーヒーを飲み、腹をくくるのがモーニングルーティーンだった。
朝のテレビを点けると、自分がいまから出勤する社名が聞こえてくる。あるいは見慣れたビルの外観が目に飛び込んでくる。そこで報じられるのは決まって、自分が働く会社の危機の原因や切迫度だった。あるいは危機を打開するための具体策や憶測だった。あまりオブラートに包まない言い方をすれば、それは債務の額やリストラの計画や買収先の候補に関する報道だ。
当時の私は(いまもそうだけど)会社にまつわるツイートを毎日するのが仕事である。たとえ朝のニュースで世間の空気がネガティブに決定づけられた日であろうとも、私には変わらず発信すべき予定があった。いくら自社への不安やバッシングが渦撒こうともお客さんはやってくるし、新製品は発売される。罵倒や心配の声の間を縫うように発信しなければならなかったあの頃の私は、毎朝、世間の空気に言葉で対峙する勇気を問われていたのだと思う。
そういう朝は案の定、ツイッターを開けばニュースへの罵声が押し寄せているし、会社の最寄り駅を出ればマイクとカメラを構えたテレビ局の人が立っていた。私はネットも道すがらも俯いてかいくぐり、さあ清濁併せ呑んでツイートをするぞと腹をくくる毎日だったのだ。あしかけ2年、そんな感じだった。
ただしここで私が言いたいのは、当時の自分がいかにたいへんだったかということではない。私が言いたいのは、朝のテレビで知った会社のニュースがすべて、私には初耳であったことだ。自分の会社のことなのに、世間より遅れて知る。あるいは自分の会社のことなのに、プロセスや意図の説明なしに、世間と同時に知らされる。リストラも買収も給料の話も、そうやって知った。
なにか問題を生じさせた企業の社員がオフィスの前でマイクを向けられ、知りませんとだけ答えて足早に去るシーンを、だれもが見たことがあると思う。私はあの、知りませんと立ち去る人のことがよくわかる。ほんとうに何も知らないし、知らされていないのだ。なのに仕事はいつも通り山ほどあるから、逃げるように急ぐのだろう。
私の場合、逃げるように急いで向かったツイッターで、さらなる「いったいどう考えているのか」「ふざんけんな」からここで書けないような言葉まで、罵詈雑言が押し寄せているのだ。ツイッターでも私は「すみません、なにも知りません。私もついさっき外から知ったのです」とつぶやいていた。
もちろん、知らないし知らされないが起こるのも無理もない。危機と呼ばれるような状況で、そんな暇はないのだ。しかし現象として、肝に命じておいた方がいい。ピンチに陥ると会社は、会社の内側に目を配らなくなる。そして内にも外にも乱暴になる。ツイッターを挟んで会社の内と外を行き来していた私には、それが強烈な体験として残っている。
日刊るかぽんず 第16話(るかぽん 著)
ただし会社を社会にひっくり返すと、私の体験もずいぶん様相が異なってくるだろう。ピンチに陥ると「社会」は、社会の内側に目を配らなくなる。「社会」は内にも外にも乱暴になる。会社が社会と地続きである以上、会社と社会は文字をひっくり返すように反転することはない。自分が働く会社がピンチに陥ることがあるように、私たちが暮らす社会がピンチに陥ることはじゅうぶんありえる。
そしてもし社会がなんらかのピンチや不都合に陥った時、そこで暮らす私たちが「知らないし知らされない」状態に置かれることもまた、容易に起こると思う。会社員が会社の内側にいるように、私たちは社会の内側にいるのだから。会社のピンチを内側で体験した私は、社会が社会の内側を粗雑に扱おうとする様子が、ありありと想像できてしまう。
しかしたぶん一点、会社と社会の仕組みに違いがあるとすれば、選挙という制度ではないかと思うのだ。私たちが「知らないし知らされない、わけにもいかないぞ」と示す手段が選挙なら、かつて自分が働く会社の行方に右往左往させられた会社員には、それこそが社会の希望にすら思えてくる。
自分が不在のまま自分の未来が決められることが、実はけっこうある。しかしそれに抗う手段を、ささやかながら社会は用意してくれている。これが会社ならそうはいかないよな、と会社員の私は選挙が近づくたびにつくづく思うのだ。
今週末の社会には、選挙がある。自分たちの未来なのに「知らないし知らされない」は、なんとも気持ちの悪いものだよ。