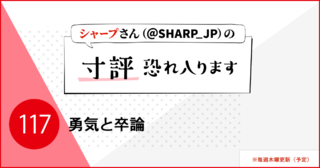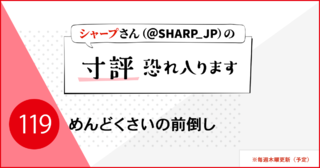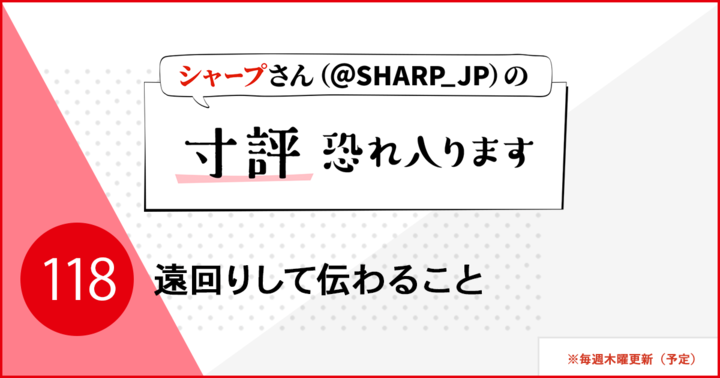
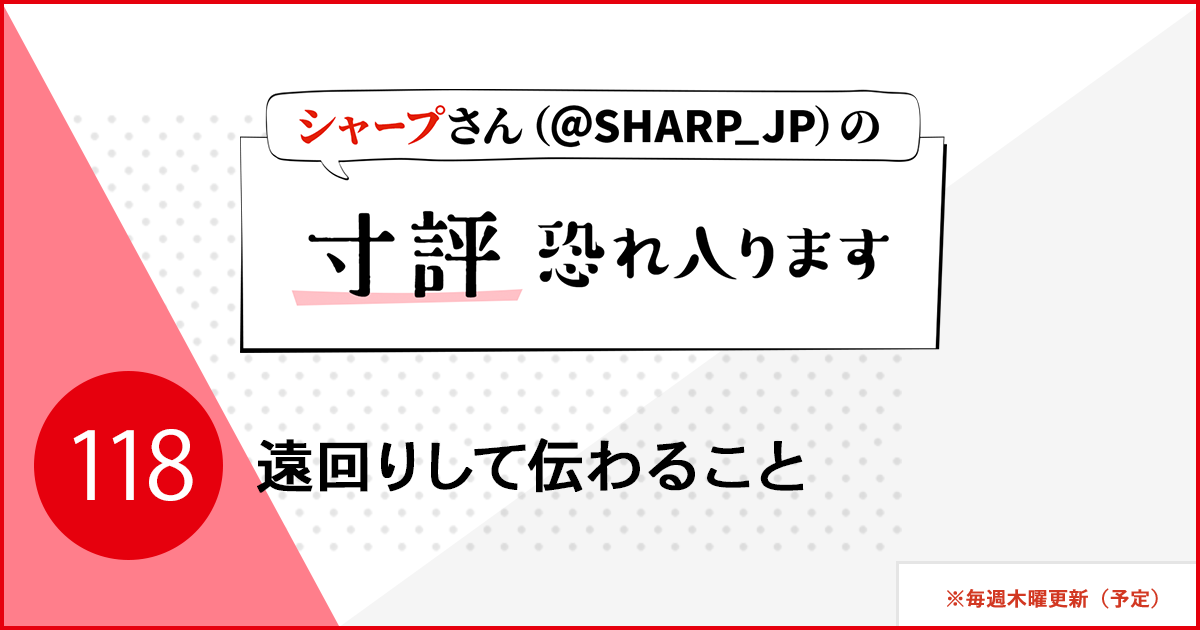
帰り道には寄り道したい、@SHARP_JPです。さいきん迂回についてよく考える。私は迷子になって迂回してしまうのも苦にならない。わざと迂回するのも好きだし、そもそも迂回という現象が好きだ。
迂回とは、なにも遠回りするとか道を間違えるとか、私たちが移動する時にしばしば引き起こす物理的な行為だけを指すのではない。だれかからだれかへ、なにかが伝わる時の道筋にも、迂回は存在する。伝達の迂回、コミュニケーションの迂回なんていう、道なき道にも迂回はある。
たとえば、言いたいことをそのまま言うだけなら小説は一行で終わる、といった言い回しも、迂回の存在を示唆しているだろう。私は必ずしも小説にあらかじめ作者の言いたいことがあるべきとは思わないが、少なくとも読者は、長い文章の連なりを追ううちに、いつのまにか自分の中に立ち上がってくる、心象風景のようなものを味わうことこそ、小説の醍醐味だと感じるはずだ。小説は、表現を迂回することで抽象的なメッセージを伝達する手段なのかもしれない。そして私は、その表現の迂回が大好きだ。
あるいは、自らのことを思い返してほしい。あなたが好きな人に「私はいい人です」と主張するのと、あなた以外のだれかがあなたの好きな人へ「あの人はいい人だよ」と吹聴するのと、どちらが結果にコミットするか。答えは明らかだろう。評判は迂回してこそ説得力が増す。もしあなたが自分の評判を上げたいなら、声高に叫んではならない。ぐっと堪えて、あなたの良さを周囲の人に沁み渡らせるのだ。
言い換えれば、口コミこそ、伝達の迂回の最たるものだろう。他人の口を伝わるうちに、評判はその威力と規模を増しに増す。私たちが日々ネット上で体験するバズというものは、迂回のモンスターとも言うべき、評判の最終形態なのだ。
それに比べれば、私の仕事のなんたる非力さ。私の仕事は宣伝である。しょせん私は、自社製品のよさを自分で声を張り上げることしかできないのだ。そこに迂回は存在しない。迂回が欲しい。私の声がどこかを迂回して、いつかだれかに届いて欲しい。きのうツイートした結果を今日求められる会社の中で、私はいつも、なかなか届かないツイートを夢想している。
先生を漫画に描いたらバズったので謝りに行った話(さく兵衛 著)
たぶん作者の実話だと思うので、これはエッセイ漫画と呼べるのだろうけど、そんなことがどうでもよくなるくらい、この作品には示唆がたくさん詰まっている。学ぶことの魅力、教えることの喜び、師匠と弟子の関係性、創作への姿勢、ここにはたくさんの哲学がある、とさえ思えてくるほどだ。気がつけば何度も読み返している。
中でも私がいいなと思うのは、評判の迂回が描かれているところだ。哲学の先生が授業を通して、哲学の魅力を伝えたいと思っている。その熱意はだが、思わぬところで実現してしまう。教え子が数年後、漫画にしたらバズったのだ。先生が説く哲学の魅力は、教え子が漫画にすることで伝わった。そのエピソード自体がまるで神話のように、迂回して伝わる強度をわれわれに教える。
一方、作者である教え子の方は、勝手に先生のことを描いた後ろめたさから、数年ぶりに先生のもとへ謝りに行く。作者が手土産に悩むマンガ冒頭は、教え子が社会人になったことを感じさせるシーンで味わい深い。もちろん先生は怒ってなどおらず、むしろ歓迎し、自分の失敗まで率直に語ってくれる。
そして話は意外な方向へ進む。先生は作者の学生時代の論文を読み返していて、その評判を遅れて伝えてくれたのだ。「貴方の哲学は一貫している」と時間を迂回して伝えてくれた先生の声は、じんわりと作者の心に染み渡った。先生と教え子の間で、迂回した思いが交差する。
ここには、双方向の迂回が存在している。感謝と評価が遅れて交換される様子を、私はゆっくりと読み返す。アクションとリターンのすばやさこそを至高とする、迂回が許されない世界で働く私は、なかば憧れをもって、この迂回を見つめてしまうのだ。