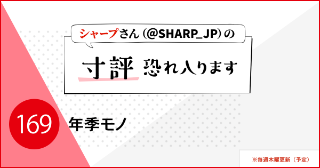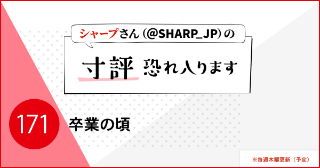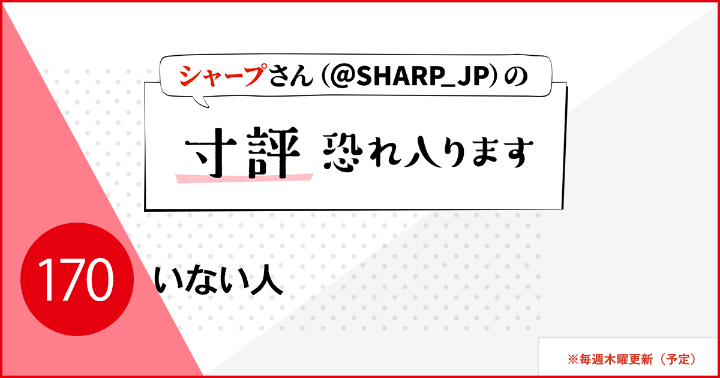
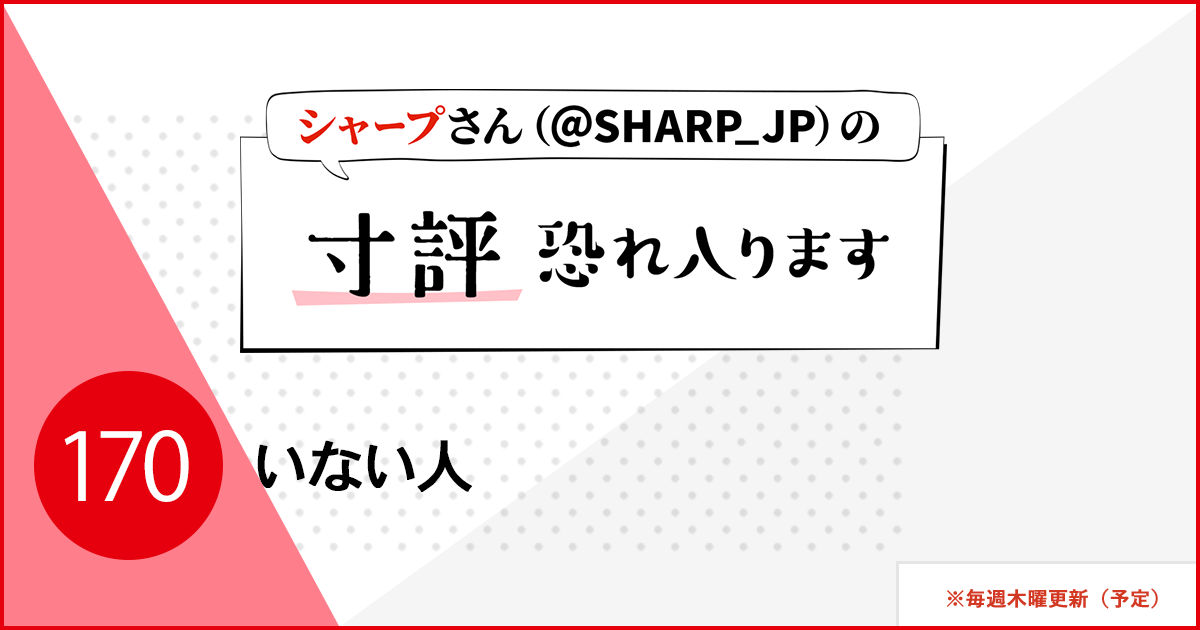
仕事が終われば一消費者、@SHARP_JP です。大多数の人は知らなくていいことなのだが、私の仕事まわりではペルソナなる、ワードというか概念がしばしば語られる。ゲームのタイトルではない。製品やサービス、広告でもなんでも、それを見たり使ったりしてほしい人物像を、とにかくむちゃくちゃ詳細に想像しましょうという、売るための伝統的な手法である。
どれくらい詳細かというと、年齢性別職業はもちろん、住んでいる場所と家族構成、趣味や特技、休日の過ごし方から装い、生い立ちにいたるまで、事細かなパラメーターを設定していく。もちろん架空の人物である。名前は仮名だが、それ以外は「そういう人いるよね」という固定観念ができるまで、とにかく属性を決定していくのだ。
なんでそんなことをするのかと言えば、いろんな人が参加して「だれかに売れるモノやサービス」や「だれかにウケる企画」を考えるときに、その「だれか」を参加者全員が共通して頭に浮かぶようにするためである。各人が勝手に届けたい人物像を考えると、アイデアや開発プロセスにブレや寄り道が発生してしまうから、とにかく目線をあわせねばという効率性の追求ともいえる。
もちろんその人物像は、さまざまな調査やデータに基づいて抽出していくのだが、なにせ項目は膨大にあるし、取捨選択する側はそもそも、売るためにその人物にすり寄りたいと願う人間である。だからたいていできあがるのは、夫と3歳の娘と暮らす港区在住35歳女性、専業主婦だがドッグトレーナーの資格保有、趣味はカフェ巡り、休日は夫のサーフィンを眺めながら家族をカメラで撮影、写真ブログも活発に運営しつつ、インスタでは料理系アカウントをチェック、友人とのやりとりはもっぱらLINEにFacebook、好きな鬼滅は宇随天元なんていう、キメラのような人物だ。もはやそれ、いる人というより、いてほしい人である。
そういう仕事に参加するのが仕事の私は「またか」とうんざりしつつ、仕事だから懲りずに「どこかにいるはずなのに一度も見たことがない人」を想像する。何度も想像してきたせいで既視感すら覚える人物は、いつしか私の脳内で妖精のようなポジションに固定された。さいきんはいつか会えればいいなとさえ思っている。私は、いない人にモノを売ろうとする、雲をつかむような仕事をしているのかもしれない。
ふなっしーの魅力(中恭 著)
このペルソナという手法は、もうひとつやっかいなことがある。私たち自身をペルソナとして固定しようとする時があるのだ。たとえば企業のマスコットキャラやSNSアカウントを考える場合を想像してほしい。そこで理想とされる企業のペルソナとはおそらく、老若男女あらゆる人に嫌われないイメージ像であろう。だからその目標に向かって、関係者がこぞってキャラクターの容貌や口調、性格などの属性を掛けあわせて、企業を人の形をしたはりぼてに作り上げるのだ。
その結果は一時氾濫したゆるキャラや、なんらかのキャラになりきったSNSアカウントのことを想像してもらえればわかると思う。つまり人畜無害だけど、ほかとは区別のつかないキャラクターがたくさん生まれた。いるのに、いない存在である。
そう考えると、あらためてふなっしーの特異さが実感される。このふなっしーを推すマンガを読めば、その余人をもって代え難さがよくわかるだろう。私たちはふなっしーのことを、ふなっしーの中にいる人も丸ごと含めて、そこにいると感じる。なぜならふなっしーの言動に、私たちはふなっしーを生んだ意志を強烈に受信するから。
つまり人が人を人と思う根拠は、その人の発する意志や信念なのではないか。ある存在を人間としてありありと想像するには、並べられた属性の各項目をチェックするだけでは足りない。人間は、イメージの合計で示されるのではないのだろう。だから私は、ペルソナという言葉をいまいち信用できないまま、のらりくらり仕事をしている。