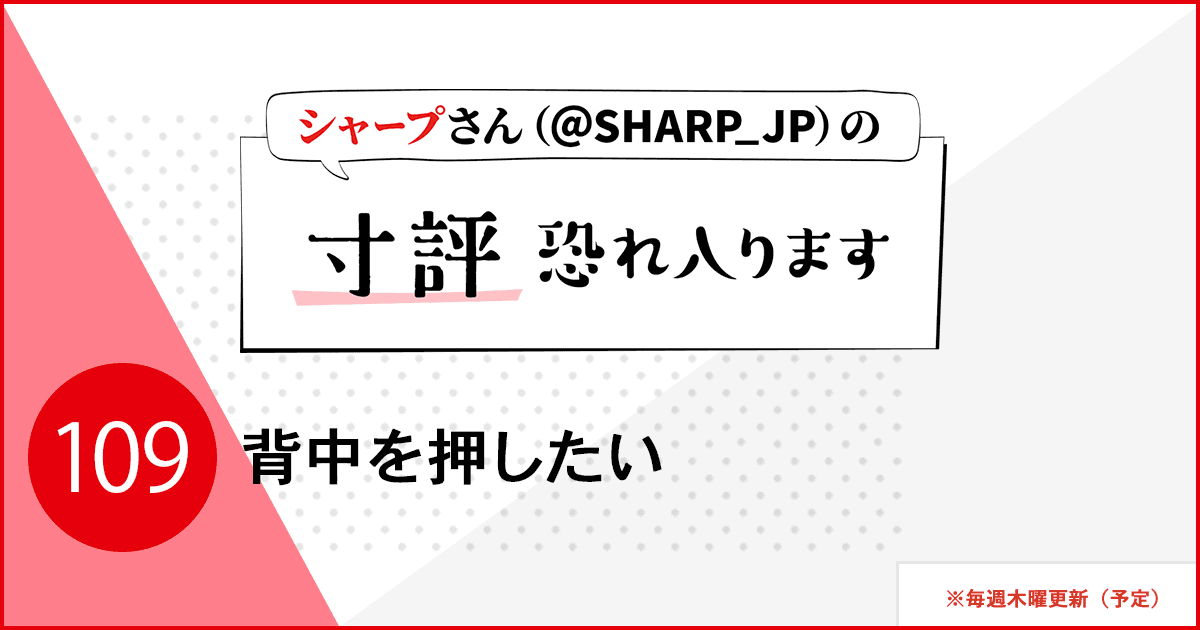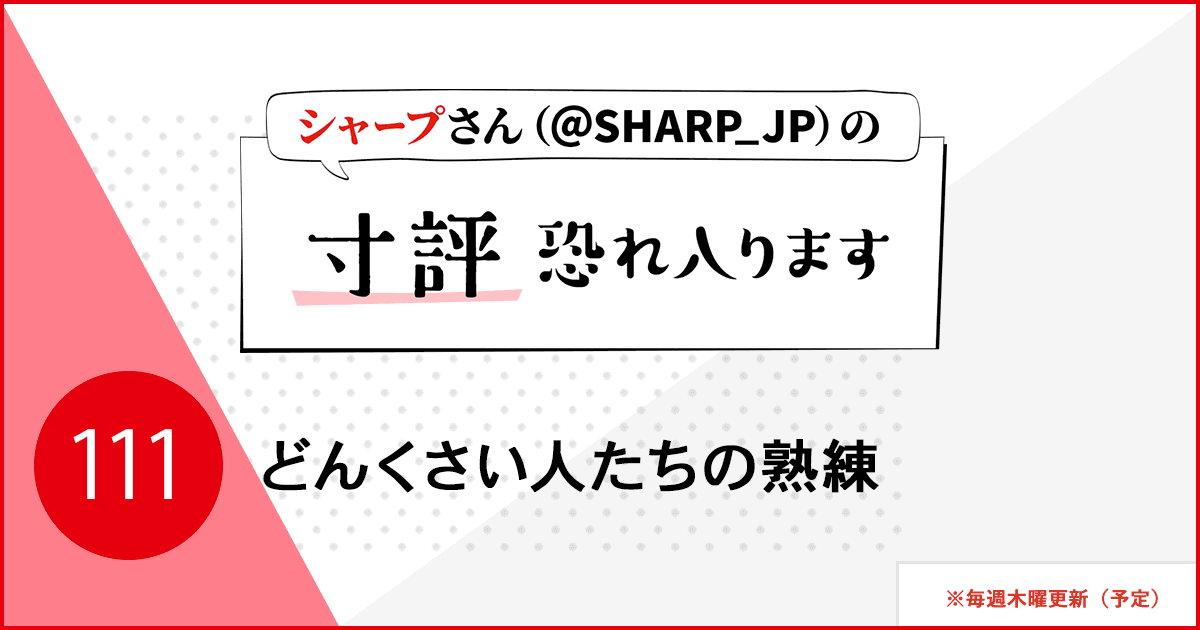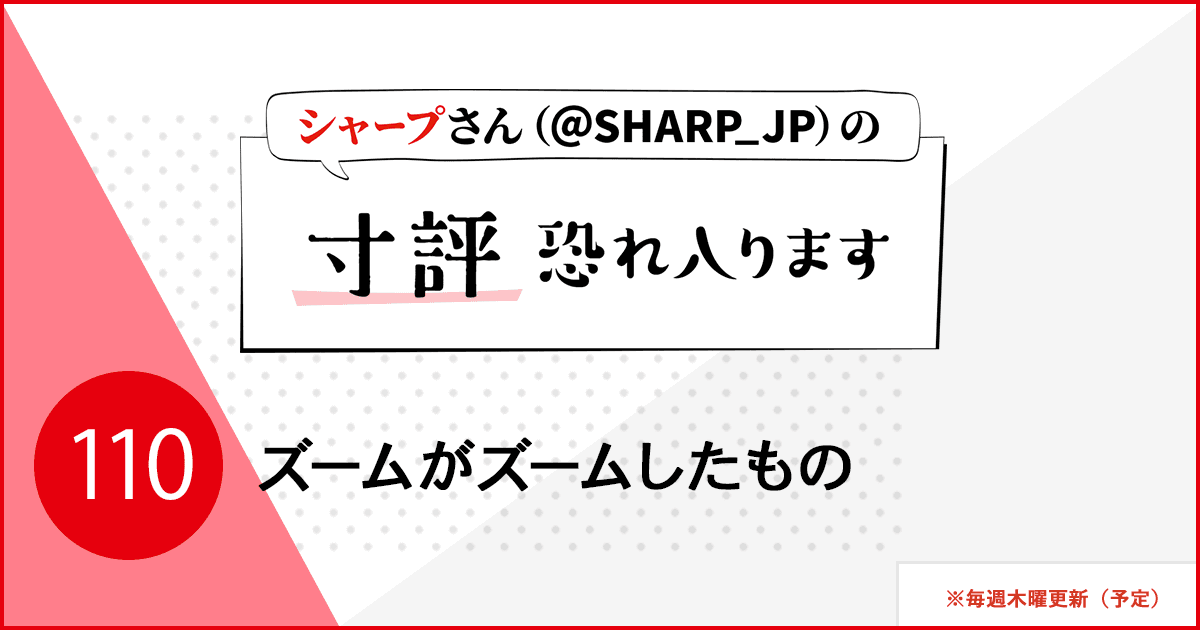
おどろくべきことにもう12月、@SHARP_JPです。いつもなら「この一年はどんな年でした?」なる質問も、師走の世間話のひとつになりうるけど、今年はそれどころじゃない。どうもこうもない。だれひとりが例外なく、世界中が例外なく、疫病というものに向き合う年になった。
あらゆることが変わってしまった。私たちの暮らしも、気持ちも、変わってしまった。というかいまも、現在進行形で変わり続けている。
私の仕事周辺では、その一変した生活を「ニューノーマル」だとか「ウィズ/アフターコロナ」などと名付けて、なんとか新しい宣伝文句にしようとしている。しかし来週のノーマルすら見通せない生活者の側に立てば、そんな名付けは空虚に映るだろうと、私は思う。なんとなく賢そうなフレーズに収めるにはまだはやい。現実はいまだ不確かで、過酷だ。
おそらく「なにが変わったか」は、これから明らかになっていくのだろう。どうにかしてホッと一息つき、生活を振り返ることができるようになった時、変わってしまったひとつひとつが、はじめて実感をともなうのかもしれない。だからいま感じている変化はプロセスだ。変化を論じることは仮説だ。
そして私はいま、ひとつの小さな仮説を持っている。それは「おじさんがかつてないほど自分の顔を見るようになった」という仮説。言うまでもなくその背景はアレ。Zoom会議だ。
私も、自分の顔を強制的に見させられることが増えた。鏡のせいではない。テレワークのせいだ。Zoomを起ちあげた時にパソコンいっぱいに映る自分の無防備な顔。まるでバラエティ番組のワイプのごとく、会議中の小窓に覗く自分の表情。
そもそもおじさんは自分の顔に無頓着だ。これまでは朝、かろうじて鏡に映る顔を見るぐらいだった平時に比べれば、Zoom会議まっさかりの今、ニッポンのおじさんが自分の顔を見る時間は指数関数的に増えているのではないか。そう予測しているのであるが、この仮説をだれか、検証してはくれないだろうか。
いずれにしろ私は「自分がいまどんな表情をしているか」が見えることは平和につながると考えている。おじさんの無自覚な不機嫌顔が、これまでいかに重苦しい会議を生んできたか。リアルタイムに自分の顔が見えるweb会議は、それを回避していくだろう。皮肉にも疫病は自分の顔を客観的に眺める時間をもたらした。自覚すれば、不機嫌は補正できる。さすれば世界と会議に、平和が訪れるであろう。
オンライン授業における姿勢の問題(近藤丸 著)
この作品にも、わたしたちの生活変化の過渡期が描かれている。作者は「寺の危機」というヤンキーとお坊さんのマンガで知る人も多いだろう。当たり前のことだが、コロナ禍を前に、お坊さんもお寺も、変化の例外ではない。
web会議中のミュート忘れは、私も経験がある。独り言が拡声器で響き渡るような経験は、ほんとうに心臓に悪い。たださすがにお坊さんのお話だ。心の声がお見通しという失敗も、どこか説話的に描かれる。
それにしてもweb会議は人との距離を確保した代わりに、顔の距離は縮めたのではないか。遠く離れて会議しつつも、わずか30センチに満たない距離で、私たちはモニター越しに相手の顔をつぶさに眺め、同時に自分の表情も視界に入れる。その主観と客観が入り混じるような状態はどこか仏教的、とはさすがに言いすぎだろうか。
それはともかく私はいま、もう少しマシな顔になりたい。美容製品だろうが、化粧品だろうが、手間と労力を惜しんででも、モニター越しの凝視に耐える最低限の顔がほしい。みなさんも気をつけた方がいい。あなたの会議中の表情、そうとうじっくり見られてますよ。