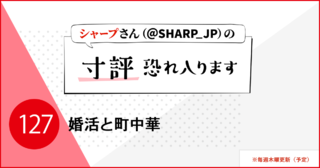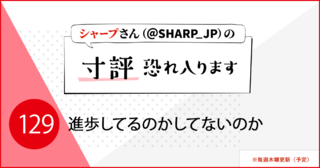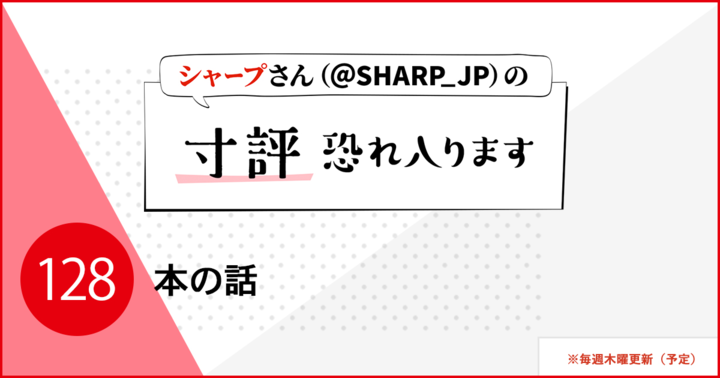
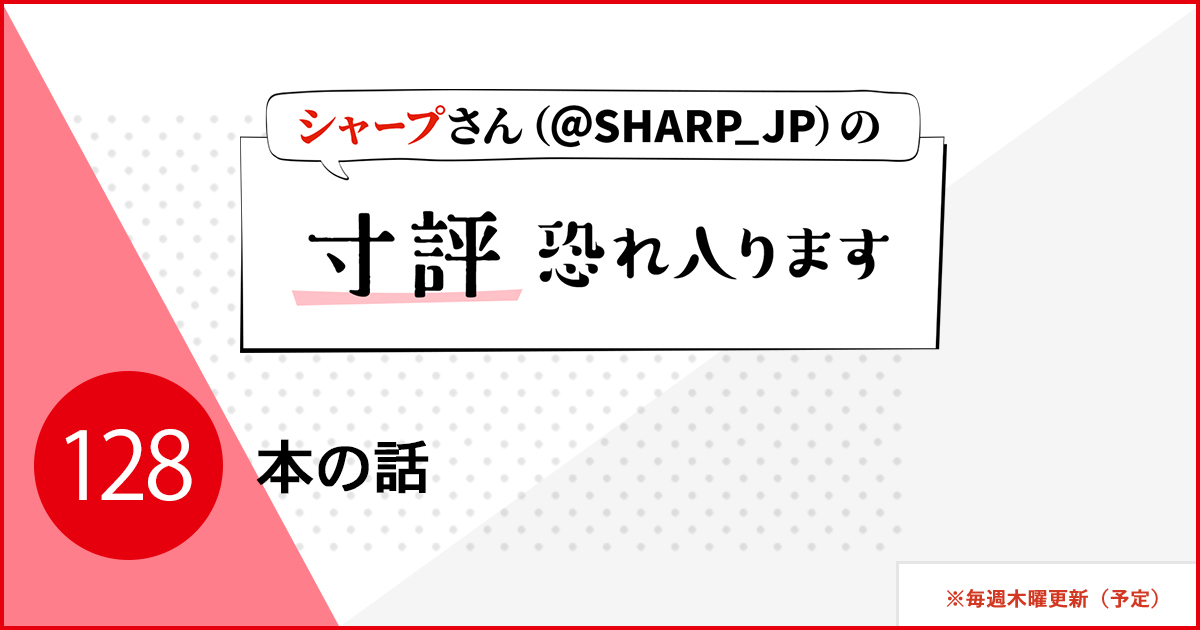
白黒つけない毎日、@SHARP_JPです。世の中には決着がつかぬことであふれているけれど、中には決着がつかないことにどうも釈然としないことがある。たとえば一時さかんに語られた、紙の本 対 電子書籍のアレだ。私の記憶では、なんだかんだいって10年も経てば、電子書籍が紙を駆逐する予定ではなかったか。
たしかkindleがはじめて発売されたのが2007年で、iPadが世に出た2010年がいわゆる電子書籍元年と呼ばれていたはず。私が勤める会社も電子書籍サービスに乗り出したため、当時はいかに本が紙から電子へ華麗に置き換わるかを、社内でこんこんと説明されたことを覚えている。
そして当時の私も、電子書籍が紙の本にとってかわる、その合理的な理由を滔々と聞かされるうちに、「それもそうだよなあ」と思うようになったのも事実だ。電子書籍は早々に紙を駆逐する。ならば私も、早々に買う本は電子にするべきだ。それが合理的というものだ。そう考えていた。
しかし、そうならなかった。少なくとも私は、そうならなかった。私の本棚だって、予定ではとっくに圧縮され、積ん読もみるみる部屋から姿を消し、本は限りなく質量を失うはずだった。だが現在、私の本棚にその兆しはない。もちろん電子書籍を買わなくなったわけではない。読書量は10年前とさほど変わらないけれど、買う前に「電子で買うか、紙で買うか」をその都度判断するクセがついただけである。
電子書籍が紙の本に置き換わらない、あるいは置き換わる速度が遅い理由は、巷でさまざまに語られるとおりだ。ここで私が述べる必要はないだろう。紙には紙の良さがあり、電書には電書の良さがある、それが並行しているだけにすぎない。しかしひとつだけ、私が「そうならなったこと」でうれしく感じることがある。
それは「私が合理的な買い物だけをする人間ではない」とわかったことだ。読書そのものが非合理的な行動だと判じられそうないそがしい時代に、なお読書を好む私は、本を買うのにもわざわざ紙を選び、しばしば部屋を狭くする選択をとる。あの当時会社で無機質に語られた、すべてにおいて合理的な行動をとる消費者像から自分がはみだしていたことに、なぜか私は安堵を覚えるのだ。
[家族日記]そろそろリアルに触れたい話(nakakihara著)
ところで本は、特に紙の本は現在、別の事情でピンチに陥っている。ステイホーム、外出自粛と、本を買いにふらりと書店へでかけることがはばかられる日常。町の本屋さんは、想像を絶するたいへんさだと思う。
ただし、このマンガで描かれているように、紙の本への欲求がパンパンに膨れ上がった人は、いま案外と多いのかもしれない。合理的でない出会いを生む場としての書店。合理的でない消費の場としての本屋。合理的に行動を抑制せざるをえない日常を送る中で、非合理な行為や非効率な店舗は、消費者にとってある種の贅沢と化してしまったのかもしれない。それゆえ本屋へ行くという行為に、憧れが募る人はいるのだろう。
私もはやく、目当てではない本に出会い、買うはずのなかった本をうっかり買い込み、そんなはずじゃなかったかばんの重みに肩を食い込ませて、ニヤニヤしながら家路につきたい。できるだけはやく、そういう日常を送りたい。