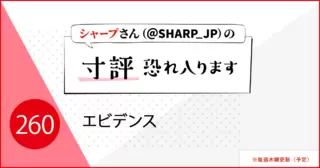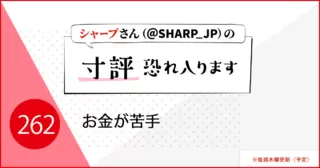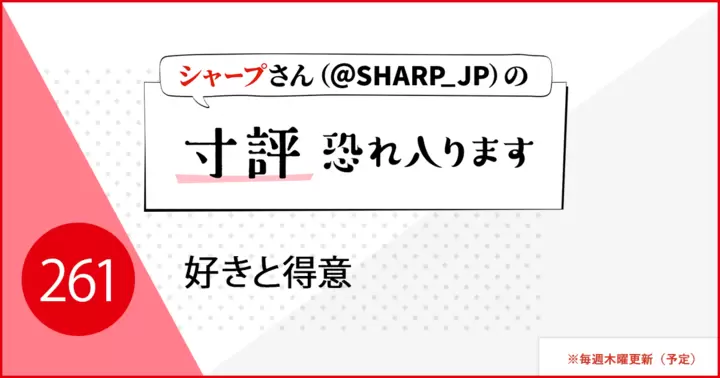
得意なものと不得意なものがあります。好きなものと嫌いなものもあります。 @SHARP_JP です。こういう文章を書いていたり、文章を書く作業が大半を占める仕事をしていたり、あるいは仕事でした文章で賞をもらったりすると、当然のように私は文章が好きなんだろうと他人から思われる。直接そうと言われなくとも、暗に私は文章が好きな人間という前提で話が進むことはよくある。
好きかと問われると、私はうなずくのをためらってしまう。読むのが好き、とは迷いなく答えることができる。でも書くのが好きかと言われると、ちょっとよくわからない。書かなければいけないから書くのであって、たいていの動機は「しぶしぶ」だ。
その先の前提でうーんと思うこともしばしばある。好きなら得意なんでしょ、と思われるのだ。お前は文章が好きそうだから、さぞかし書くを得意としているにちがいない、という圧である。もちろん私だって、うまく書けるとうれしい。うまく書きたいし、書き上げることができたという感触がなによりの好物である。むしろその爽快感を得たいがために、それを書く動機にする傾向がある。
とはいえ、私はうまく書けたを目指して書くけれど、そこにはいつも悶々とした時間がある。しぶしぶで嫌々な時間。自分で自分を探る時間。なにも思いつかない時間。あのまんじりともしない時間を思えば、とうてい私は文章を書くのが得意なのか、わからなくなってくる。私は文章を書くのがたぶん好きだし、たぶん得意だ。たぶん。けれど手放しで好きだとも言えないし、得意だと胸を張って宣うほどの確信はない。それが私の、率直な前提である。
それにしてもわれわれは、すぐ好きと得意を結びつけてしまう。それを好きならきっと得意だろう。それが得意ならまちがいなく好きだろう。私たちは、絵が好きと聞けば、その人が絵を描くのが上手だと迷わず思う。運転が得意と聞けば、その人は車が好きなんだと無邪気に解釈する。しかし時に、料理が好きと料理が得意には意外なほど距離があるように、好きと得意には思いのほか乖離がある。
自戒をこめて言うけれど、好きと得意は一致するという思い込みは偏見だ。好きと得意の乖離に自覚的な人にとって、好きと得意の無自覚な混同はいつだって暴力的な指摘になりうる。絵とか音楽とか、巧拙を自分からも他人からも問われる創作を志す人にとって、好きと得意の乖離はとりわけ敏感な部分ではないか。
僕の好きなこと(みほはは 著)
それでなくとも現実は残酷だ。好きだからって、上手いわけではない。好きだからって、優秀なわけではない。逆の場合だって、それぞれの地獄があるのだろう。上手いからって好きとは限らないし、優秀な人は必ずしも好きな分野で優秀さを開花させているわけでもない。
好きと得意が合致しないことなんて、ほんとうはいくらでもある。だけど私たちはその複雑さから目を逸らして、好きだから得意あるいは得意だから好きという、単純な因果関係を支持してしまう。幼い子どもにとって、その短絡さがどれほど無慈悲なものか、このマンガを読めば痛いほどわかると思う。あらゆることを「はじめて」というかたちでしか出会えない子どもは、好きと得意が一致しない経験にさらされ続けているのだ。
だけどわれわれにとって、とりわけ子どもにとって、好きと得意の不一致に、ひとつくらいは光明があるのではないか。つまりは好きこそものの上手なれ、である。好きである限り、その人は得意の途上にあるのだ。好きならそれがいずれ得意になる可能性は大いにある。なぜなら、私たちは好きじゃないと続けられないから。好きと得意は一致しないかもしれないけど、それは合致への道のりだと思えば、後ろめたく感じる必要はない。
好きを続ければ、たどりつく境地がある。好きは得意の途中なのだ。