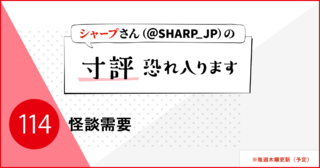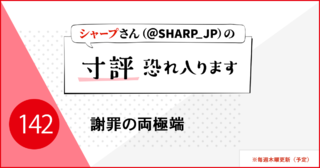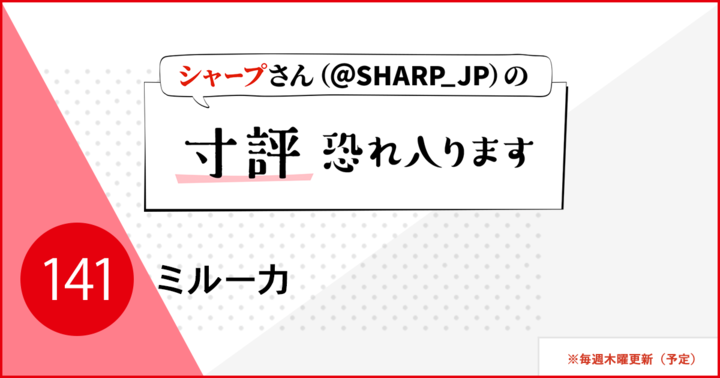
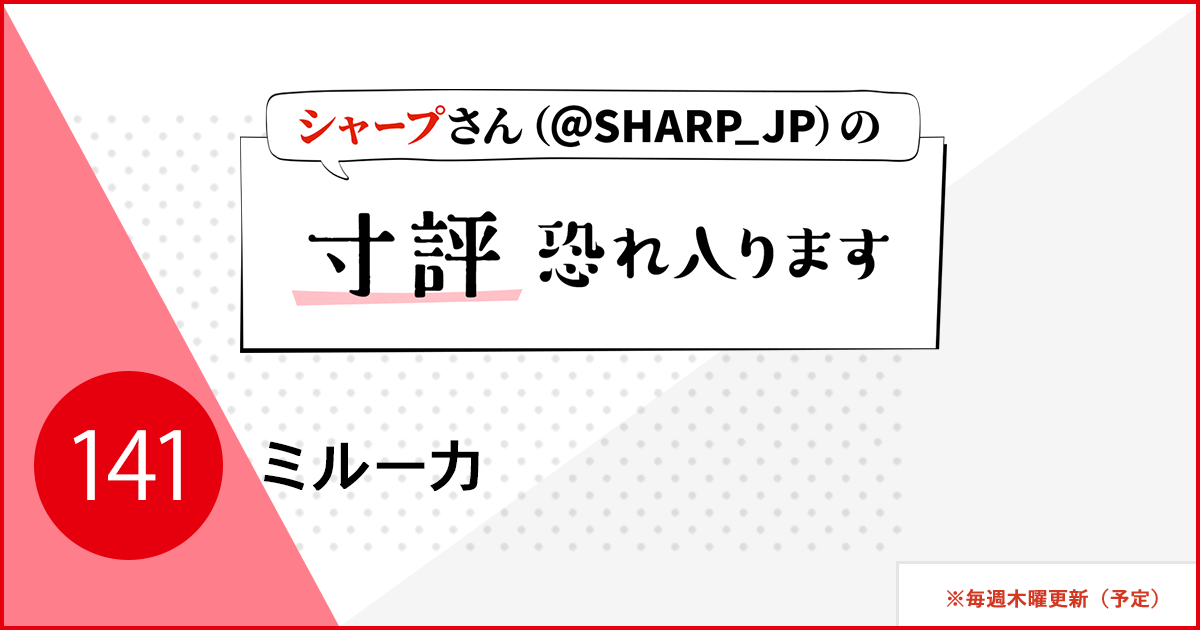
シーイング イズ ビリービング、@SHARP_JPです。唐突に大きなことを言い出して恐縮だが、ここ10年で人類は「見る力」を飛躍的に向上させたと思っている。いまやどこかへ行く前にグーグルマップを覗くなんて当たり前だし、世界中の行ってみたいところを見るために、日がな一日地球を縮尺することだってある。旅行が制限された今なら、それすら慰みになる人も多いだろう。行ってないのに、見たと言える時代だ。
一年半にわたる災厄で、われわれは行く場所や行く手段をすっかり奪われてしまったけれど、よくよく考えてみればモニターやスマホ越しに、会いたかった人を見る機会は飛躍的に増えたのではないか。音楽や観劇のように、現実の同じ空間を共有することはなかなか叶わないけれど、そこで活躍したであろう人が案外近くで、それも手のひらの中で、親密で素朴な姿を垣間見せることが増えた。配信ライブにしろ、トークイベントにしろ、もしそれが実地で開催されていれば、物理的制約から選ばざるをえなかった諦めを軽やかに奪ったとも言える。地方に住む人なら首肯するだろう。行くことは減ったけど、見ることは増えた。
それからオンライン会議や飲み会である。なんだか目新しかったzoom飲み会なんて、ぜったいに飲みに行かない人や、住むところが離れてしまったり、疎遠になってしまった友人と再会するきっかけとしても機能したはずだ。一方オンライン会議は、参加者がみな画面に正対して並ぶから、いつもは伏し目がちにやり過ごしていた退屈な会議も、居並ぶ顔をまじまじと見るチャンスと化した。人は人の顔を見る手段が増えたのかもしれない。
デバイスと通信の進化によって、あるいは災いによる生活や行動の変化によって、われわれは見る機会を増やし、見る力を養った。百聞は一見にしかずを加速させた人類が、今後さらに「見る力」を亢進させるとしたら、それはなにだろうか。私は「見立て力」ではないかと睨んでいる。見たものの背景や文脈を読み取ったり、見えているものを別のものになぞらえる力だ。
河原にて(サクラミナト 著)
見立てるには集中力とコツがいる。その難儀さを、百合に興味をもった少年たちが河原で思い知る。隣に座る友だちを脳内で女の子に変換しようとする思春期の男子はあまりに微笑ましいけど、見えているものを別のものになぞらえるのは、たしかに力がいる。
かつての日本人は、庭の草木を水の流れに見立てたり、盆栽に宇宙を見立てたりしてきた。喩えているのに喩えていると言わない和歌や文学も、読む側に見立て力が必要な文化である。そこではきっと、見立てを見るための経験や教養が、文化としての強度を高めてきたのだろう。一朝一夕には参加できないところが、文化としての魅力でもあるのだ。
だから少年たちには修練が必要なのだ。力を養ったその先に楽園があるなら、そこへいたるには努力を要するだろう。おそらく「見る力」を強化させた人類は、次の楽園を目指す。選ばれし者が次に手にするのは「見立て力」だ。なぜなら、手練れの腐女子の方たちを見てみるといい。見立て力を培った人の楽しそうな様子を。そこに脳の楽園がある。私は「見立て力」こそが「見る力」のネクストステージだと思うのだ。
ただし、注意すべきこともある。見えないことを見るのは問題だ。私が仕事とするツイッターにも、書いてないことを見る人がやってくる場合がある。書いていないことや言ってないことを見ることは見立てではない。それは幻覚だ。そこに楽しさも文化もない。ましてや楽園でもないことは、さいきんの殺伐とした文字を見て、多くの人が感づいていることだと思う。見えないことを見るのは要注意、である。