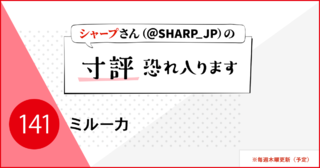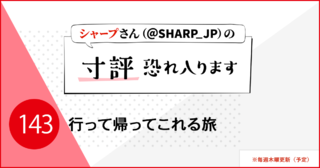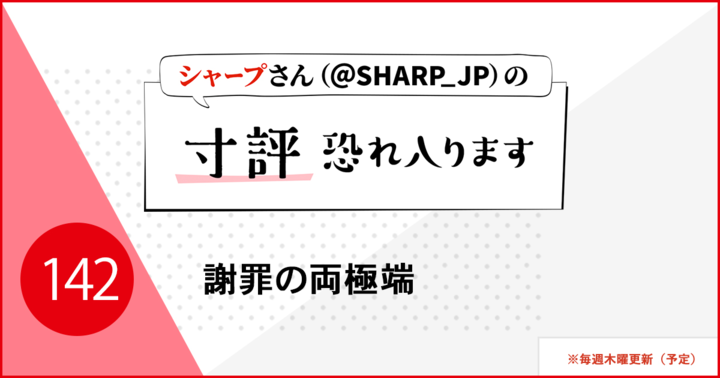
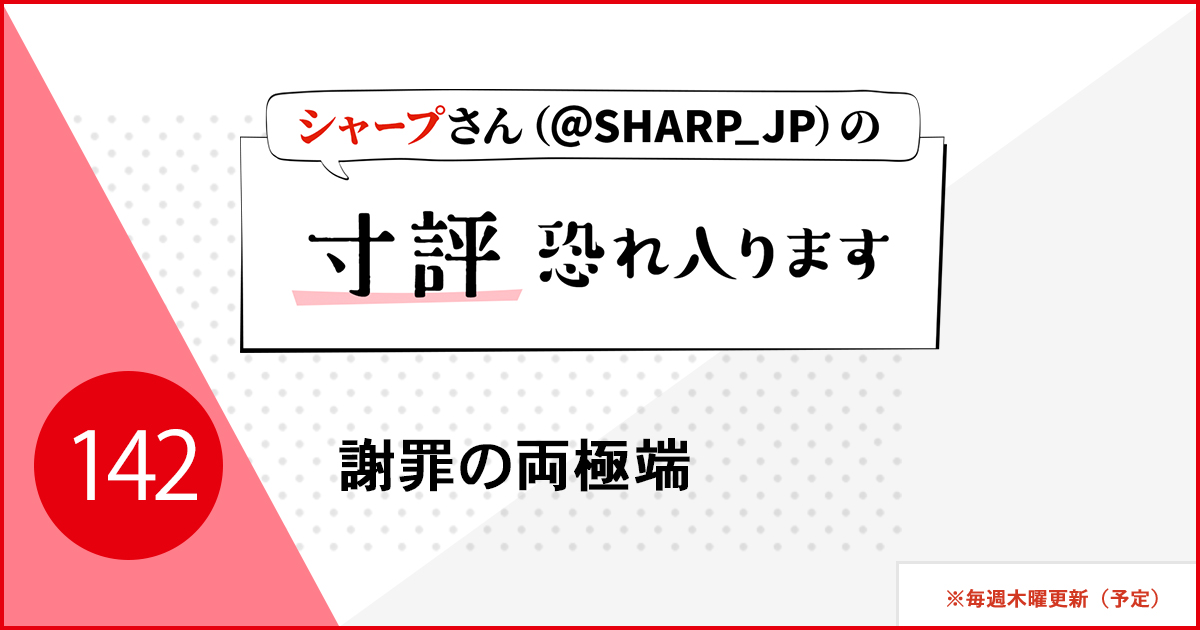
申し訳ございません、@SHARP_JPです。連日、謝罪を目にした。謝罪を目にしない日はなかったと言ってもいいほどに。おそらくそこのあなたも同じ印象だろう。謝罪にいたる経緯や背景について、それぞれ個別な問題をはらんでいるし、なにより当時も今も知り得ない事情があるはずだから、私はそれについてなにも語ることができない。というよりもむしろ、連綿と続く謝罪が明らかにした歪みのようなものが私の過去を突き上げる気がして、じっと考え込んでしまう。具体的な心当たりがあるわけでもないのに、振り返った過去それぞれにおいて、自分はどういった感覚でその時生きていたのかを思い出そうとしている。だからいまは、なにも語ることができない。
しかし個別の内容を別にすれば、謝罪は繰り返し接するほどにその重みは薄れていきがちだ。とりわけ世間に向けて発せられる謝罪のメッセージは、丁寧さと慎重さとスペースの都合でもって最大公約数な言葉が選択されるから、必然的に似通った文章になる。どこかで聞いたことのあるような、色のない似通った文章を浴びると、人は書いた主格を見失ってしまう。それは校長先生のあいさつや、会議で肩書きを誇示する会社の人の説教にどこか似ている。
一方、政を担う場所で、あるいは私たちが働く職場で、謝ったら死ぬのかと思うほど、ぜったいに謝罪しない人がいる。われわれの社会は謝罪ひとつとっても「する」と「しない」で両極端に引き裂かれ、もうなにがなんだかわからなくなっているのかもしれない。頭がくらくらしてくる。
誠意のこもった謝罪(shucreams 著)
だから、こういうマンガを読んでホッとする自分がいるのだ。謝罪をめぐるわちゃわちゃしたやりとりは、もちろん気心の知れた間柄だからこそ成立するのはわかっている。しかし謝罪するにしろ、しないにしろ、ぎりぎり愛嬌と呼べるような弁明の隙間があってほしい。その隙間をユーモアと解す国や文化があるのかもしれないけれど、できれば私は、私たちが暮らす社会にも、まるで水曜どうでしょうのような押し問答が成立する場所があってほしいと、心のどこかで思っている。
おそらく私も、謝罪と紙一重な仕事をしているのだ。そういう気の抜けない感覚はずっと培ってきたつもりだけれど、愚鈍な自分を知っているからこそ、それが完璧でないこともよくわかっている。私はいつだって失敗する。だからせめて、私が謝罪をする時はこのマンガにあるように、「ふーん、なかなかいい誠意持ってんじゃん…」と思ってもらえるような、気心の知れた間柄を少しずつでも築いていけたらと願っている。難しいことだが、それが私にできる誠意なのだと、なかば自戒のように心に刻んでいるのだ。