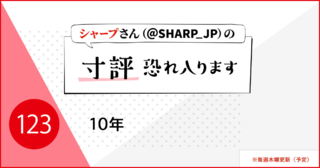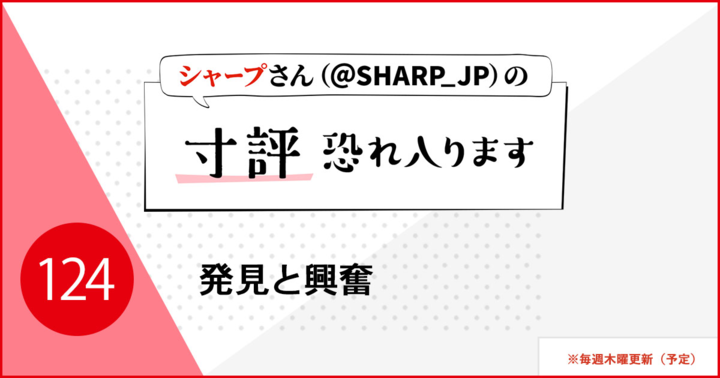
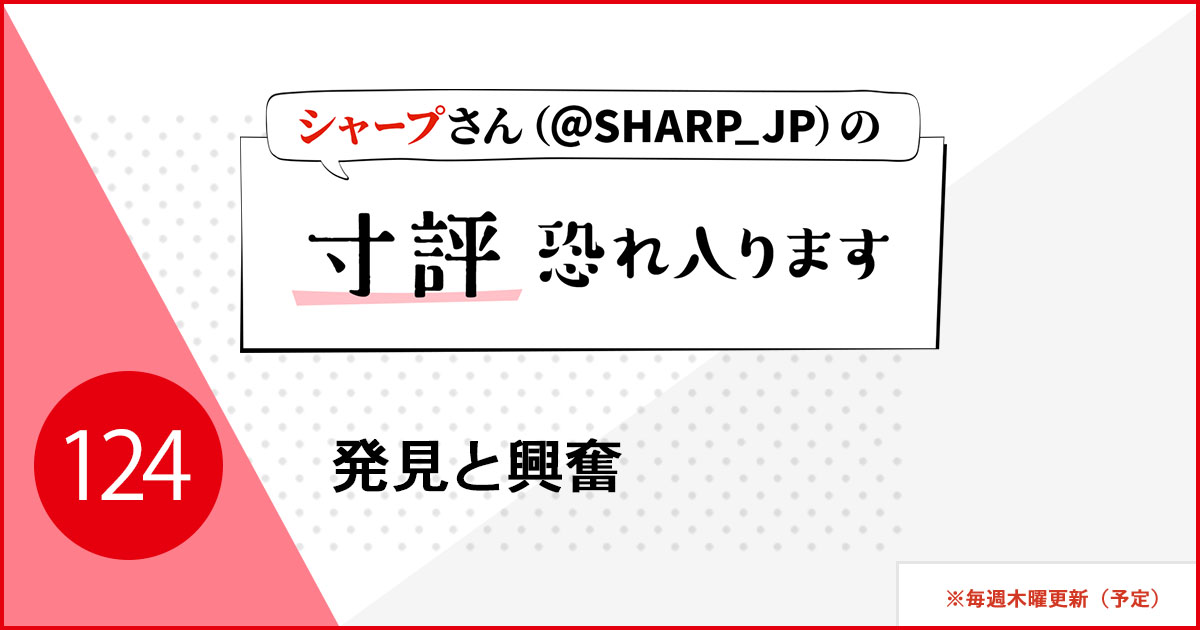
ドキドキしてますか、@SHARP_JPです。興奮、などと書き出すと、すわ性的な話かと興奮するのが、ネットのわれわれの悪いところですが、私がしたいのはそういう話ではない。もうすこしこう、客観的で静かな興奮とでも呼びたくなる、ドキドキする経験だ。
たとえば、極めて高い完成度や作家性を誇る映画を観てしまった時、人は静かに興奮すると思う。いまならシン・エヴァンゲリオンを観た人が典型だろうか。もちろん映画だけでなく、文章や絵、あるいは音楽でも、そういうことは起こりえる。
広く芸術とくくられる表現の中には「なにか圧倒的なものに触れてしまった」感覚をもたらすものがあるのだろう。偶然ある曲を耳にして、雷に打たれたような衝撃と静かな興奮が身中を走る経験をした人は多いはずだ。
と言っても、いま私が話したいのはそういう興奮とも、またすこし違う。作品に触れる興奮というより、作品が生まれた場に居合わせた興奮とでも言えばよいだろうか。それも同時代的に経験する種類の。
音楽の例を続けて恐縮だけど、私は多感な時期にダンスミュージックに傾倒していた。長らく音楽を聞き続けている人には同意してもらえると思うのだが、特にダンスミュージックは周期的に、発見や発明がある。それは新しいリズムだったり、音色だったり、スピードだったりするのだが、世界のどこかのだれかが見つけた発明が、瞬く間にダンスミュージックの「モード」となることがあるのだ。
多感な時期の私が経験したのも、そういう音楽の同時代的なうねりみたいなものだった。特に発見されたのがビートだったせいもあり、ダンスミュージックの骨格ががらりと変わってしまうような、劇的な体験。当時は、世界中で同時多発的にレコードがリリースされ、それをひたすら聴いていた私は、まるで音楽が毎週アップデートされるような気分で、ひとり興奮していた。
それは、だれかの作った曲の新しさに興奮したというより、音楽が書き換わる現場に参加できた喜びに興奮していたのだと、いまならわかる。だから時代が変わっても、あの頃の私はセックスピストルズが出てきたイギリスにもいただろうし、日本語ラップ黎明期の東京にもいたはずだ。ボカロが歌い出したニコニコ動画の前にも、あの頃の私はいたのだろう。
龍と虎 第1話 銀杏の葉(いくたはな 著)
このマンガを読んだ私は、いま静かに興奮している。そしてその興奮をうまく言葉にできないうちに、私はあの頃の私を思い出したのだ。
もちろんこの作品には、魅力的な要素が具体的にたくさんある。清潔でしゃれた絵。ほほえましい日常。かわいい女の子。古風な会話。なぜか上杉謙信。しかも武田信玄。つまりは龍虎の戦国エピソード。読んでいない人にはさっぱりわからないだろうが、これらは紛れもなく、このマンガの魅力なのだ。だが、それだけではこの興奮はどうも説明しきれないのである。
たぶんここには「発見と発明」が存在するのだ。この作品を読んだ私は、いままで見たことのない「掛けあわせ」を体験し、作者の発見に興奮した。
それは言い換えれば「ジャンルの誕生」に遭遇した興奮なのかもしれない。あの頃の私が、新たな音楽ジャンルの勃興にリアルタイムで夢中になったように、いまの私はこのマンガの中に新しいジャンルを発見し、衝撃を受けている。つまりは、新たなタグが爆誕した瞬間だ。
私とここを読むあなたは、もう体験してしまったのだ。大げさにいえば、歴史の目撃者と呼ばれるような人々も、こういう類の興奮を覚えたのではないか。
なんだよ、百合と戦国武将って。最高じゃないか。