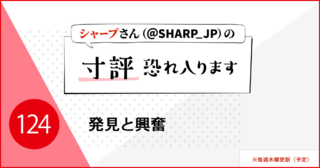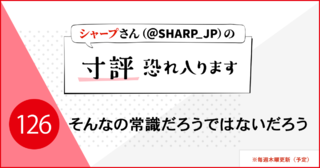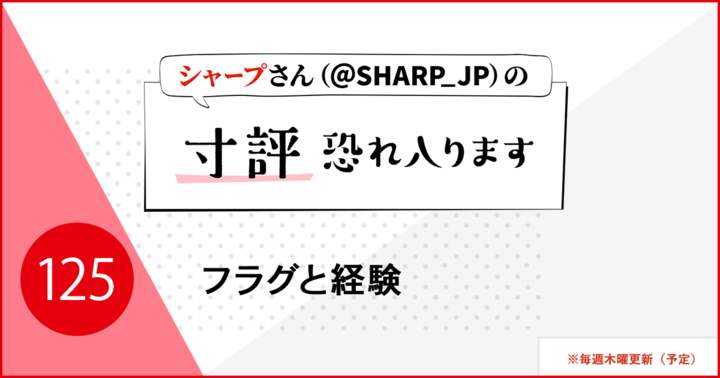
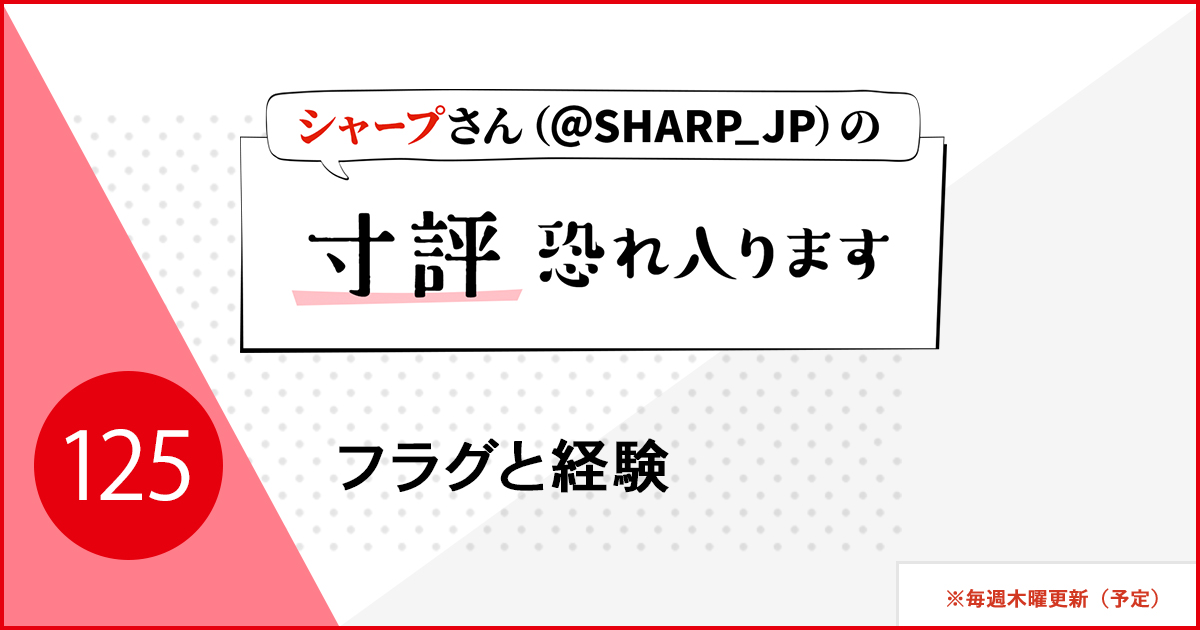
春ですね、@SHARP_JPです。雪柳や木蓮を見かければ「もうすぐ」と思うし、桜のつぼみを目にした日には「来た来た」と心の中でつぶやく。花は春のフラグだ。もちろん春だけではない。沈丁花。クチナシ。ひまわり。金木犀。紅葉。イチョウ。椿。折々の季節において、街は花のフラグに満ちている。
フラグとは、それを見ると「その後に起きることへ見通しが立つ」というサインだ。われわれは未来のことなんて皆目わからないけれど、フラグが立った事物については唯一、未来を予想できる。花を見て季節が訪れる経験をくり返してきたからこそ、その花が私たちにとってのフラグになるのだ。
見る→起こるという因果の体験(とはさすがに大げさだけど)が逆にわれわれの日常へフラグを立てていくのなら、年齢を重ねると感知できるフラグは増えて行くのだろう。そう考えると、なんだか人生の見晴らしは年々よくなりそうに思えて、年を取るのも悪くない気がしてくる。
といっても、フラグとはもともと現実の世界で語られるものではなかった。物語の演出として、繰り返し使われてきた「お約束」のことを指していたはずだ。ホラー映画で率先してはしゃぐヤツは真っ先に邪悪なものに襲われるし、誠実な美男美女は必ずサバイブする。トーストをくわえて走る人はその直後だれかとぶつかるし、しばしばメガネを外すと容姿は輝くのだ。異世界に転生したらいろいろあるけど最強。だいたいそうに決まっている。
これらのフラグはもちろん、現実の世界ではありえない。少なくとも私は見たこともないし、体験したこともない。それでもなお強固なイメージであることは、われわれがいかにフィクションの世界で「お約束」をくり返し経験してきたかを物語っているはずだ。
私たちは現実の世界でも物語の世界でも、経験を通してフラグを増やすことができる。もしそれで生きるのが楽しくなったり、人生が清々しく感じるのであれば、フラグを感知する力とはもはや教養と言えるのではないか。
俺がゾンビでゾンビが俺で(nougagomibako 著)
「ふたりが組んずほぐれつ階段を転がり落ちる」がフラグであることに異論の余地はないだろう。ふたりが組んず解れつ階段を転がり落ちればなにが起こるか。入れ替わるのだ。当たり前だ。ほらこのマンガでも入れ替わった。
ただしフラグはお約束だからこそ、それを裏切るという選択も作者には可能だ。ここでも、作者の小さな裏切りが試される。通常は人格が入れ替わるとその環境も入れ替わるのが、階段落ちフラグの妥当な未来だ。入れ替わったふたりは、家も生活も友人も入れ替わる。しかしそうならなかった。状況はなにも変わらなかった。なにせゾンビだから。ここは恋が芽生えそうな男女の入れ替わりではないのだ。だからこの作品を読む側には、鮮やかにフラグが裏切られた快感がもたらされる。私も笑ってしまった。
ただし私は重箱の隅をつつくような、ゾンビ愛好家だ。ちょっと物を申したい。ゾンビと人間の人格が入れ替わる。その時にもしゾンビは人格と身体が分離しているという前提に立つなら、人間の身体に入ったゾンビの人格は、その身体を食おうとするのではないか。追いかけっこはそこで休止するのではないか。ゾンビの経験を重ねて、ゾンビフラグの感知能力を上げてしまった私は、気になってしょうがないのである。
そんなことを言う私は、教養のない粗野な人間だろうか。