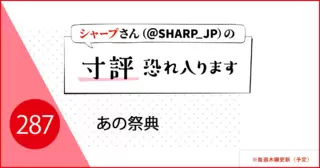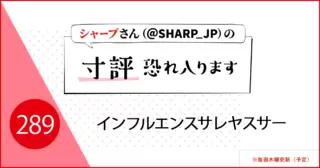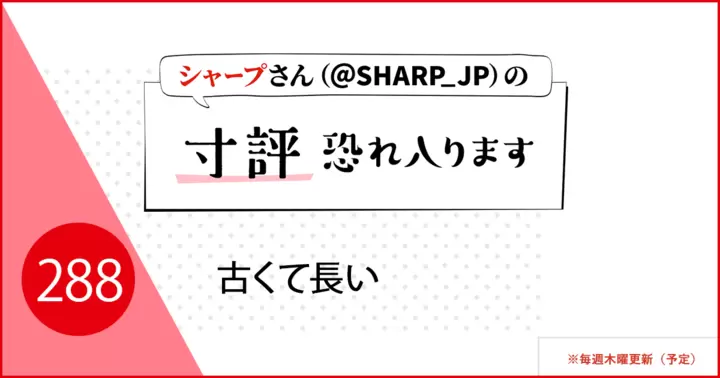
猛暑お見舞い申し上げます、 @SHARP_JP です。自覚があるかどうかはともかくとして、私は一般的に見ても、そうとう長く同じ仕事を同じ会社で続けている。異動というものが定期的に強制執行される、比較的大きな企業に勤める人なら、なおさら驚かれるケースかもしれない。
ただし私自身は仕事なるもの、行きがかり上に取り組むのみという意識の低さを引きずっているので、今の仕事が長いとか短いとかいう感覚が希薄だ。ただのんべんだらりと毎日を仕事し、時におもしろいなと思い、時にやってられるかと思いながら、テキストと時間だけが積み重なってしまった。
だから自分の仕事の長さを実感するのは、いつも他人の言動がきっかけになる。ついこの前も同業者だという人と名刺交換をした際、私のツイッターキャリアが何年かという会話になり、「ぼくが中学生のころからやってる」とつぶやかれた感慨に虚をつかれてしまった。
中学生が高校生になり大学生を終えて社会で働くまで、私は同じことを同じ場所でやっていたのだ。おそらく向こうからは、私が地蔵か、あるいは路傍の木にように見えたにちがいない。そういえば大学で講義を受け持った際も、自己紹介として私の仕事のきっかけを説明しようとした時、それが彼ら彼女らにとってはスマホを持つか持たないかという小学生のころの話だと急に自覚が襲ってきて、絶句してしまったこともあった。
私たちは日々を過ごす時、時間の長さに無自覚になりがちで、そのぶん他人の物差しで過去を計測される機会に遭遇すると、時間の長さの実感が一気に押し寄せてくる。とにもかくにも、私は長い時間を同じ場所で同じ仕事に費やしてきた。それはつまり、とあるSNSがそれほどの時間をかけて私たちの生活を占有し、SNS自身が歳をとりながらも、常に新しい人を呼び込み、その身体を大きくしてきたプロセスなのだろう。
のびのび童話(ノビタ 著)
かつて私は、SNSのことを、とりわけツイッターのことを、第2の世間と呼ぶことがあった。現実では決して起こりえないであろう出会いがあったり、会うことなく気心が知れる仲間ができたり、遠くにいた存在がスマホ越しなら身近に感じることができたりと、現実の世間にある心的・物理的な距離をバグらせる点こそSNSの醍醐味であり、現実とは別の方向へ成熟する世間だと考えていた。
しかし第2の世間は、だんだん薄れつつある。昔からそこにいる人ほど、そう感じると思う。いまやSNSは、第2が第1にどんどん近づいて、ただの世間と化した。つまりは、年齢も性別も嗜好もばらばらな人が行き交う、いまあなたが暮らす空間と同じなのだ。唯一ちがうとすれば、第2の世間は多様にばらばらな人の肩がひんぱんにぶつかりあう、距離だけが妙に近い、狭くて騒々しい空間であることかもしれない。
たぶんそこでは、世間の最大公約数が次々となくなっていくから、「みんなで話す」ことがどんどん難しくなっていくのだろう。私が10数年前のできごとを小学生のころとして話し直せなかったように、これからさらに世間話が困難なSNSになっていくのかもしれない。
その難しさは、このマンガで改変される「もとの昔話」が共通の理解として通用しない世間と考えると、すこしわかりやすいと思う。さすがにこれはだれもが知ってるだろう、という前提が通用しないことが増えているのは、みんなうすうす気づいているかもしれない。
現実の世間の代替としてSNSが第2の世間としてあるのではなく、今後は現実の世間と鏡写しの世間を行ったり来たりしなければならないのなら、なかなかの体力が必要になるな、とため息をつきそうになる。苛烈な世間が2つあるなんて、人生が苛烈すぎやしないか。