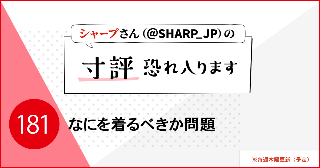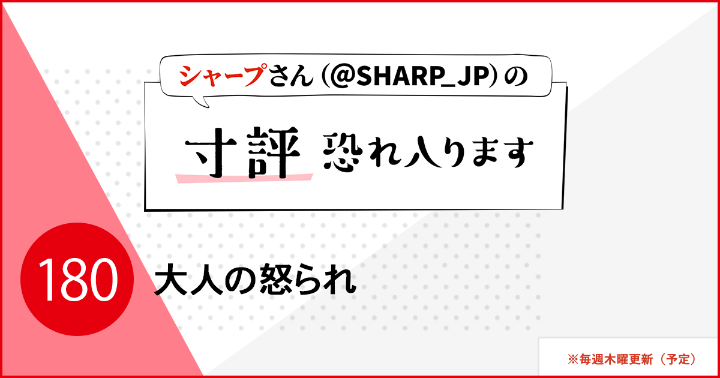
褒めるの推奨、@SHARP_JP です。働き出してそこそこの時間が経ったけど、ずいぶんと怒られることが減った。親や先生からとりわけよく怒られる子どもではなかったし、大人になってからの「怒られ」は相手をしつけるとか導くというより、詰めるという作為が大半なような気がして、自分が怒られるのも、だれかが怒られるのを見るのも、けっこうしんどいものがあった。ようやく「怒られ」が減ったのは、自分が周囲を耐え抜いたのか、周囲から自分が諦められたのか、ほんとうのところはわからないけれど、昔に比べれば心は穏やかだ。よかったよかった。
とにかく大人の「怒られ」は、ほぼ「詰められ」だ。そして「詰められ」はたいてい「なんでできないの?」とか「どうして失敗したと思う?」といった、一見開放的に見える質問からはじまる。だがその質問は自由な返答が許される、決してオープンなものではない。
たとえあなたができない理由や失敗の原因を述べようとも、そう分析した理由や原因の原因をさらに尋ねるエンドレスな質問ループにいつしか巻き込まれていくだろう。あるいは、あなたができない理由や失敗の原因を「他者のせい」にしたとたん、その態度そのものに叱責が向く。結果的に「自分のせい」しか選べない、自責一択の細道が「詰められ」の規定ルートなのだろう。考えるだけでうんざりしてくる。
つまりは、生殺与奪を握られているのだ。質問をいつ止めるかを決めるのは相手。回答が正解かどうかを決めるのも相手。詰めを終えるのは、圧倒的な権力を振りかざした相手次第なのだ。だから自分が生殺与奪を握られるのも、生殺与奪を握られた人を見るのもつらい。大人の詰められは(ひょっとしたら部活のような若い人の現場も)ただそこにしんどさを撒き散らすだけだと思う。
アパレル店員の裏事情 第29回(渡とら 著)
程度の差はあれど、相手に回答の生殺与奪を握られる場面はほかにもあった。このマンガで描かれるような、「似合う?似合わない?」とか「どっちがいいと思う?」という場面だ。
こういうケースで多くの人は経験上、あらかじめ正解が決まっていることを知っている。だから慎重に、あるいはあえて軽く、回答を保留しながらヒントを探るのではないか。しかしその行為こそが、正解にたどり着けない落伍者のレッテルを貼られることも多い。近しい人間こそ、即答が可能であるはずだからだ。だが私たちは往々にして、誤答する。悲しいほどに、誤答する。
しかしこのマンガがひとつの光明を示してくれた。「私はあなたがうれしい方が正解だと思う」そこには詰めも詰められもない。生殺与奪を握られる前に自ら差し出すことができる間柄こそ、愛と呼ぶのかもしれない。われわれはこのマンガで、少し賢くなったのではないか。