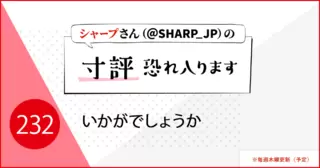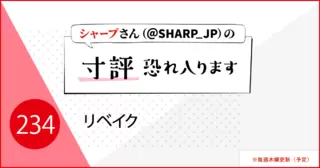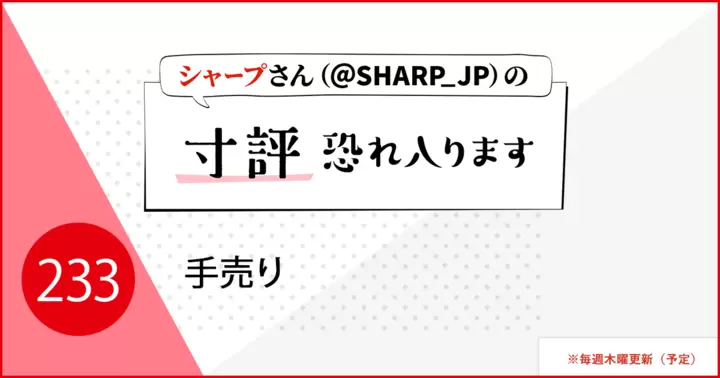
俺か、俺以外か、その他大勢か、@SHARP_JP です。世の中には二種類の人間がいるなどとおもむろに切り出して、すぐ人を二つに分けようとするのはインターネットにいる大人の悪い癖ではないか。私も例に漏れず、なにかと二種類に分けたがりの性質がある。ただ私がなにか格言めいた二分を言おうとも、そこになんの説得力もないから、だいたいは黙っている。
ただし仕事においては、つきあう人を半ばリトマス試験紙のように判定する二分法を、私は持っている。それは「手売りしたことがあるか、ないか」だ。私は手売りしたことがある。そして手売りしたことがある人とは、仕事をしていても相性がいいし、つきあいが長続きする傾向にある。それはたぶん職業観の底の方にある、矜持とかスケール感と呼べるような感覚に、お互いどこか通ずるところがあるからだと思っている。
きわめて大雑把に言えば、世の中の仕事は作る仕事か、売る仕事かに分けられると思う(言ってるそばから二分してしまった)。手段はどうあれ、私はどちらかというと売る仕事が長いから、同じく「売る」に関連する生業の人とたくさん仕事をしてきた。そして、手売りの経験がある人はその仕事や発想にどこか手触りがあり、手売りの経験がない人のアイデアには、いつもつるんとした印象があった。
それは、お客さんに直接モノを売ったことがある経験の有り無しと言ってしまえばそれまでなんだけど、実は手売りするモノを「自分で作った」という手応えも響いているのだろうな、といまは考えるようになった。ただし手売りの経験がある人の方が優れていると言いたいわけではない。むしろ私は、手売りの経験がない人の方が、大きく売るためのアイデアや行動力に長けているとさえ思っている。つまりこれは、どちらが商売上手かというより、どちらが体温を感じるかという、ただの美意識の話だ。
標的は同人誌即売会(田淵有希也 著)
私はなにを手売りしていたかというと、CDやTシャツである。自分や自分が参加した演奏を収録したCDを売ったり、自分の所属するバンドのようなものの名をTシャツにして、ライブの後に売ったりしていた。みなさんご明察の通り、それらがたくさん売れたわけではない。たくさん売れていれば、私はいまのような仕事に就いていないし、ここで文章を書くこともなかっただろう。
けれどその時の感覚は、いまもずっと通奏低音のように、仕事をする私の中で鳴っている。たいして売れないから、買おうとする人が現れると売る側がびっくりしてしまうあべこべな照れ臭さも、売れないなりに売れる数を予想する苦労も、結果的に売り物が同じ音楽を志す人との物々交換のツールと化すオチもすべて、対面で売るという行為を手触りに変換する、手売りの記憶だ。だからいまでも私は、モノを大々的に売らなければいけない時にも、つい手触りを求めてちんまり仕事をしてしまうのだろう。
そして手売りと言えば、同人誌即売会だ。自分で描いて印刷して製本して手売りする。このマンガではなぜかヒットマンがサークル参加している。手売りするこの人たちの仕事は、きっと手触りと体温があるにちがいない。その仕事を見てみたいと思うけど、殺し屋稼業に加担するわけにはいかないのだった。私は「あいつがやった」という手触りが残る仕事に親愛の念を持つけれど、それはつまり、ヒットマンとしてどうなんだ、ということでもある。