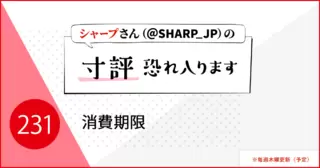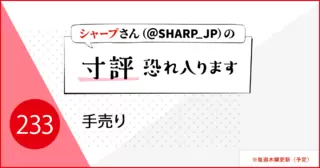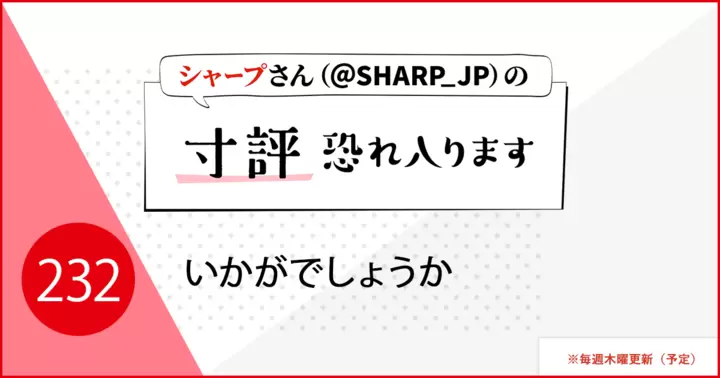
あなたが落としたのは銀の斧ですか、金の斧ですか、それとも落としてなかったんでしたっけ、@SHARP_JP です。仕事の場において、私は「いかがでしょうか」と聞かれるより、聞くことの方が多い。圧倒的に多い。それはつまり、社内における私の地位が低い証左なのが少し悲しいが、とにかくお伺いを立てさせていただく仕事人生なわけである。
なにをするにしても、なにを買うにしても、なにかと上司にOKをもらわなければいけないのが会社の仕組みでもあるので、いかがでしょうかと聞くことの多い人は私だけではないだろう。いわゆる決裁というやつである。決裁を取る労力が労働の大半を占める勤め人のみなさん、お疲れさまでございます。
もちろん私も例外ではない。とりわけ私の仕事は、アイデアとか演出とか企画の実現を目指すケースが大部分を占めるので、比較的抽象的なモノゴトについて偉い人へ説明したあとに、「いかがでしょうか」とお伺いする期間が長かった。「Aをすればリスクは高くともいかほど儲かり、Bを選べばリスクは低いが儲けはこれほどです、さあいかがでしょうか」とお伺いするならまだしも、私の場合は「Aはここが素敵で、Bはあっちがキレイです」とか「タレントAさんはこの層に人気絶大ですが、Bさんはこっちの層に広く知られています」と説明した上で、重々しく「いかがでしょうか」と尋ねるわけである。
抽象的なモノゴトを「いかがでしょうか」と聞かれても、聞かれる方は困ってしまうだろう。数字や円で導かれるモノゴトの可否ならまだしも、かっこいいとか美しいとか人気だとか、ふわふわした単位で判断を迫られても、聞かれた方は「知らんがな」という言葉が喉元を迫り上がってくると思う。だいたい聞く方も、あまりの抽象度に困っているのだ。だから抽象を具体に見えるように、私もあれやこれやともっともらしい理屈をひねり出そうとするけど、たいていは混沌を増す結果になってしまう。
だから私はそういう時、できるだけ「いかがでしょうか」という言葉を使わないようにしている。いかがでしょうかと聞く代わりに、私はこっちが好きです、と先に表明するようにしてきた。偉い人の喉から出かかる「知らんがな」を、ここはひとつ「私を信用してくれ」で先んじて封じる作戦だ。それがうまくいってきたのかはわからないけど、私はまだ、同じような抽象度の高い仕事をしている。
読み切り 第175話(小林操 著)
だいたい「いかがでしょうか」は、やっかいなのだ。このマンガで描かれているように(ここでは「どうですか?」だけど)、往々にしてわれわれは「いかがでしょうか」と聞かれても、そもそも「いかがもなにもない」のである。「どうですか?」と言われても、すぐに「どう」を検知できるほど、私たちは変化に敏感でもないのだ。いいか悪いかすらわからない宙吊りな状態は、われわれの日常生活にしばしば発生する。
しかし「いかがでしょうか」「どうですか?」と聞かれた時、われわれは「答えることがなにもない」状態をつい恥じてしまう。なにもない状態を、自分が鈍感であったり、見識がないように感じて、自分がバカなせいだと思ってしまうのだ。だから思ってもいないことをあわてて口にして、取り繕おうとする。
これが仕事の場合なら、偉い人は自分の「なにもない状態」が自分の偉さを脅かすように感じてしまって、つい余計なコメントをしてしまうのだろう。そして仕事は順調に滞り、労働時間は延びに延びていく。だから「いかがでしょうか」は、聞くのも聞かれるのもやっかいなのだ。