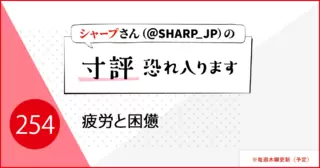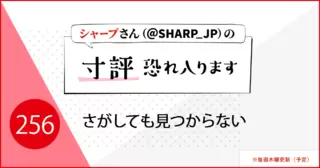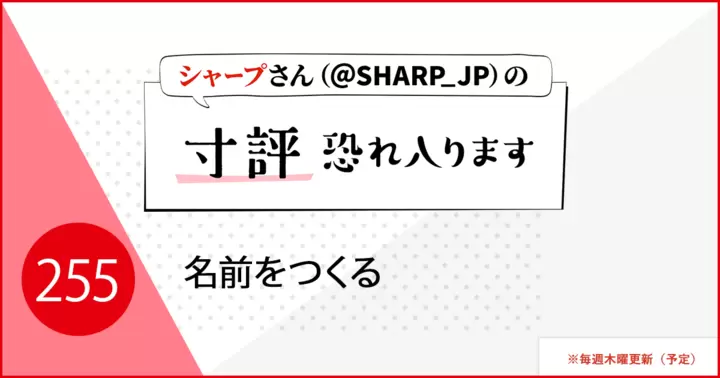
名前をつけてやる、@SHARP_JP です。仕事でモノの名前をつけたり、ロゴマークをたくさん作ってきた。もちろん私は本職のコピーライターやデザイナーではないので、自分が名前の候補を考えたり、ロゴやマークのフォルムをカタチ作るわけでもない。ある製品や機能があり、それを短く端的に呼称あるいは記憶してもらうために、どういう意図をこめて名付けをし、どんな印象を感じてもらうロゴにすべきかを考え、それに基づいて出てきた本職の人たちの案を取捨選択する仕事である。そういう名付けやデザインにいっちょかみする仕事をちょいちょいやってきた。なので私が作ったと言うのは、やはり語弊がある。
私が作ったかどうかはともかく、それなりの数のロゴやマークを世間に差し出してきたことはたしかだ。そのうちのいくつかは、いまも検索されたページに表示されていることもあれば、遊びにいった知人宅の家電に見つけることもある。目にするたびに私は「おお君、まだ健在でしたか」と、よそよそしさとおどろきを含んだ懐かしみを感じる。見かけなくなった野良猫に、離れた場所でとつぜん再会するのに似ているかもしれない。
というのも、消えてしまう名前やロゴの方が圧倒的に多いからだ。それが名前やデザインのせいであれ、別の理由であれ、ほとんどはだれの注目を浴びることもなく、だれかの記憶に残ることもなく、ひっそりと世の中から消えていく。膨大な用事や情報にあふれる世界にあって、生まれたことすら気づかれることなく消えるなんて、なんらめずらしくはないのだ。そこに、次から次へと新製品や新機能を投入することを宿命づけられた企業が、自らすすんでひとつ前の自分たちの製品や機能を上書きし、なかったことにしていく。なかば強迫観念のような企業活動が、消える名前やロゴに拍車をかける。
だれにも知られず、だれにも覚えられないまま、世の中から退場していった名前やロゴマーク。それらが生まれる過程に立ち会ってきた私は、存在ができなかった存在をたくさん知ることになった。消えた名前やロゴの数々を知る私は、いま多くの人が親しむネーミングやロゴに、類まれな強運と不断の努力を見る。そして同時に、消えた名前やロゴの累々とした亡霊を、著名なマークの奥に幻視してしまう。
私たちは知っているモノの中からしか、モノの存在を認識できない。知らないモノは、知られないまま存在するのではない。知られないモノは、存在がないのだ。むしろ消えた名前やロゴマークは、存在ができなかったモノの、かすかな存在の痕跡なのかもしれない。
自分でロゴ作ったら大変だった(松島 菜摘 著)
マンガ家は自分の作品の名付けやロゴマークをどうしているのか、ずっと気になっていた。まだタイトルは自分でつけるとしても、人の目を引くタイトルマークなどは、書籍の装丁が作者とはちがう専門のデザイナーがいるように、別の人間が担うのだろうか。
いずれにしろ私が仕事として関わってきた名前やロゴの制作とは、まったく事情が異なるのだろう。生まれた子の名前を考えることと、売れそうなモノの名前を考えることが根本的にちがうように、自分で自分の作品の名前やマークを作ることは、私の知るプロセスとは親密さも切実さも段違いだろうと思う。
そういうちがいが、このマンガで垣間見れておもしろかった。作者もいろんな事情や思いを抱えて、タイトルやロゴを作るのだろう。その知らない苦労が、マンガを読むとよくわかる。ただしひとつだけ、作者と私の仕事に共通する苦労があった。時間がないことだ。締め切りや納期に追われる苦労は、だいたいどこもいっしょなのかもしれない。