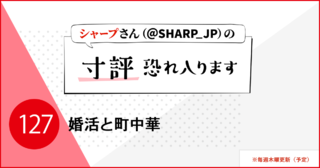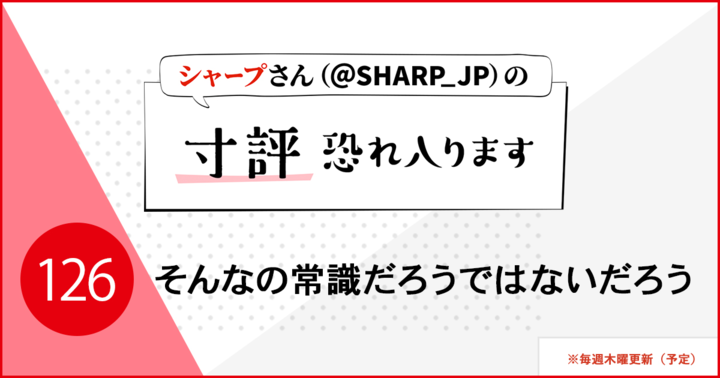
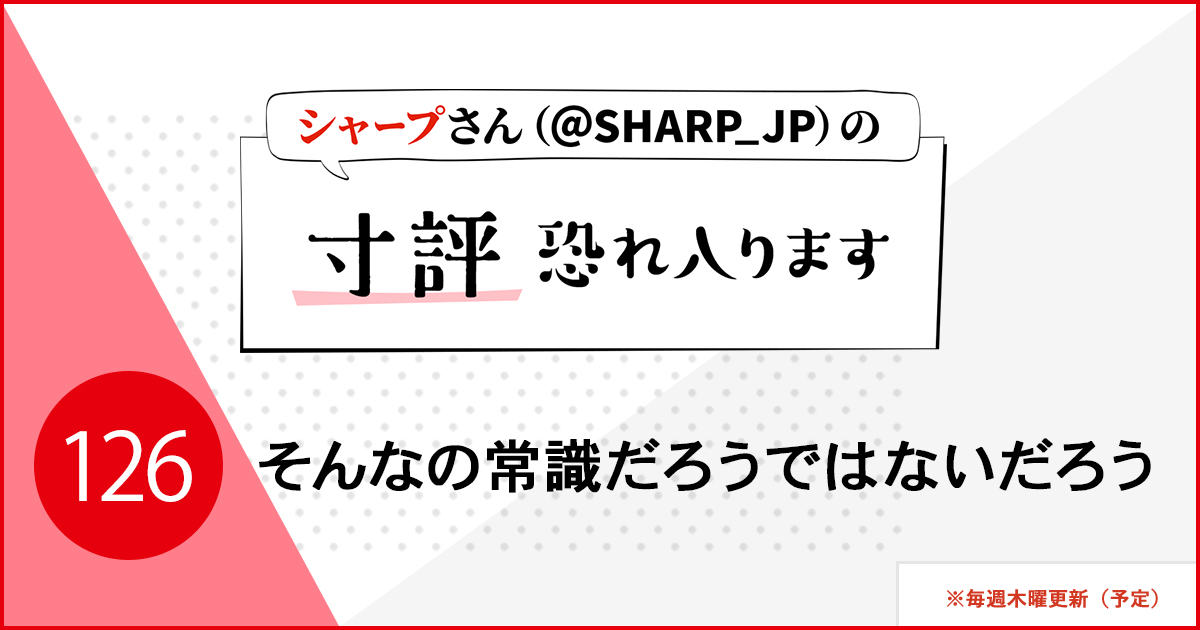
嘘みたいな毎日、@SHARP_JPです。諸行無常とか有為転変、あるいは生々流転とか飛花落葉とか、この世のものは変化し続けるという意味の熟語は、けっこうたくさんある。そういう熟語を私たちは「儚い…」とため息をつくような使い方をする。
しかし最近の世の中はどうか。このめまぐるしい変化はいったいどういうことか。もはやついさっきまで当たり前だと思っていたことは当たり前ではない。振り返ればなにもかも変わってしまったと、ため息つくような展開だ。世の儚さに遠い目をして使っていた四字熟語も無常観が消え去り、ただただ目の前で万物が転がり豹変する様を表しているようで、言葉の味わいも変化してしまった。
食事の仕方、会話の仕方。出かけ方。移動の仕方。飲み会の頻度。
働き方。打ち合わせのやり方。休み方。連絡の手段。
名前の呼び方。性差の捉え方。家事のやりくり。子どもの育て方。
音楽の聴き方。映画の楽しみ方。スマホを手にした暮らし。
世紀の祭典すら何度も何度も軌道修正を迫られるのだ。
世間の空気。吸い込む空気。かつて空気を読めと呼ばれていた空気は、いまやどんどん更新の頻度を上げている。
すっかり変わってしまったことなんて、まだあるだろう。つまりは、常識が通用しないのだ。常識が通用しない時代というと陳腐に聞こえるけど、ほんとうにそういう時間を、私たちは息を詰めながら、きょろきょろしながら生きている。常識は容易に揺らぐ。そのことをいま、私たちは痛烈に感じている。
見えない当たり前をこわしてくれた先生のこと(かくた 著)
かつて常識は、「そんなの常識だろう」というあり方によって、常識であり続けてきた。だれかがふと呈する日常の疑義に対して「そんなの常識だろう」という返しが成立することこそが、常識が常識であり続ける根拠なのだ。それゆえ常識はがんこだった。
しかし今はもう、そうではない。人智を超えた災厄を前に、あるいは不当な目に耐えてきた声なき人の声の前に、もはや「そんなの常識だろう」の方こそ成立しないのだ。
それはこのマンガのように、いま私たちは「当たり前と思い込んできたもの」が揺さぶられる体験を、みんな同時に体感していると言っていいのかもしれない。「見えない当たり前」に囲まれた田舎の少年が、実は「そんなの当たり前だから」と思考停止していたことに気づく。無事に卒業式を終えた少年は、当たり前が壊された痛快さのあとに、自分の頭で考えることの喜びを知った。当時の先生は「思考を続ける」ことをこそ、教えたかったのではないか。
常識は常識の内側にいる人たちの「そんなの常識だろう」という思考停止によって常識であり続ける。常識を疑うのは、常に常識の外にいる人だ。だから常識のラインを挟んで「なにが悪いのかわからない」と「なにを言っても伝わらない」の巨大な溝が生まれるのだろう。
いま私たちは、年齢によって、性別によって、住む場所によって、あるいは勤める会社によって、容易にその溝の思考停止側に居続けてしまうことを知りつつある。そしてまた、常識のラインを動かしたり、破壊する快感も知りつつある。
だからこそわれわれは次に、マンガの少年が明るく笑えるようになった地点を想像すべきではないか。新しい常識が昨日よりもマシな明日を更新するものであるためには、私たちが思考を続けた先にある「世界の見晴らし」を思い描くべきなのだ。