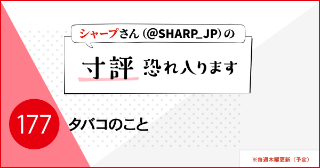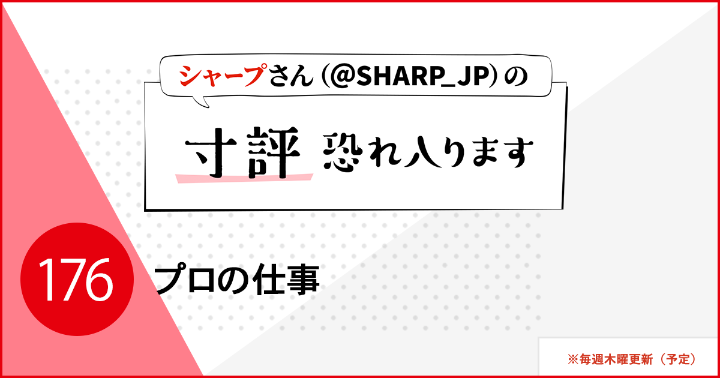
なにかのプロかもしれない、@SHARP_JPです。ときどき、プロの仕事を見る時がある。プロの仕事と言っても、この道二十年の精緻な技巧とか、一寸の狂いもない完璧な納品とか、非プロのこちらがひれ伏すしかないクオリティのことを指すわけではない。もちろんそういう品質の極みみたいな世界に触れることは「プ、プロ…」と唸らされる最高の体験だけど、私はもう少し、プロの仕事は間口が広いと思っている。
料理していて「なんか足りない」と思った時。具体的な調味料と量を指示され、言われた通りにやってみると「そうだったこれだった」という味になる。自分とだれかの写真や絵を並べてみた時。「なんか違う」と思っていたら、違っているポイントを具体的かつ無数に指摘してくれる。あれこれ組み合わせてもいっこうに「なんかダサい」が改善されない時。手渡されるままに服を着たら、「なんでいままで」と臍を噛みたくなるような、おしゃれに振れた自分が鏡の中にいる。
つまりは「なんか違う」に的確で具体的な指示を返してくれるのが、プロなのだと思う。われわれの「なんか違う」に理由を見出し、その対処法を知っている人のことを、私はプロと呼べるのではと考えている。モヤモヤして像を結ばない「なんか違う」という感覚を、目に見えるかたちに分解してくれる人が、われわれの周りにたしかにいる。
平凡な私たちだってそれなりに感覚は鋭敏だ。だから私たちが、折に触れて感じる違和感はほとんどの場合、正解である。ただし平凡な私たちには知見も経験もないから、その違和感を具体的に分析することができない。私たちはいつだって、違和感の出どころがわからないのだ。だから違和感の因果関係を実際に体感した時、はじめて「なんか違う」の「なんか」が取り払われて、私たちは感嘆する。
そう考えると、社会はプロに満ちているのだろう。家族や友だち、上司や同僚に、プロの仕事を見る時があるはずだ。私もせめて仕事においては、だれかの感じる違和感を目にみえるかたちで分解できる程度には、プロでありたいなと思っている。
デザイナーが、「創英角ポップ体」しか存在しない世界に行く話(中恭 著)
グラフィックデザイナーなんて、「なんか違う」を分解して、目の前で違和感を「なんか違ってた」と過去形にしてくれる、典型的なプロだろう。このマンガはダサいフォントしかない世界という、ちょっと特殊な異世界転生ものかもしれないけど、なんか違うというモヤモヤをデザイナーが鮮やかに解決する話だ。
私も広告の制作過程で、文字間を調整したりレイアウトを変えることで一気にかっこよくなる様子を見せてもらってきたから、これはあながちファンタジーではないと思う。最近はそうでもないのかもしれないけど、ふつうの人は文字をフォントとして見る感覚すらないのだ。だからこそ、プロの仕事にシンプルに感嘆するのだろう。
プロは違和感を可視化する。なにがどうしてあなたが「なんか違う」と感じているのかを解析してくれる。そしてそれを解決する。私たちはそのビフォーアフターに喜ぶけれど、プロの仕事を見た時の感嘆は、問題が解決した安心感だけではないはずだ。
私たちは、「なんか違う」の「なんか」が取り払われた時にようやく、その「なんか」が雰囲気ではなかったことを知る。「なんか」が具体的な要素で構成されていたことを知ったとたん、そこの世界が因果関係を有した姿として、クッキリと見えるようになる。私たちはその世界が反転する様子に感嘆するのだ。どんな世界であろうが、プロはかっこいいのである。