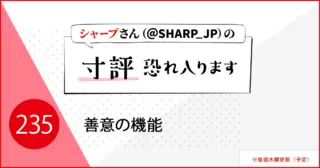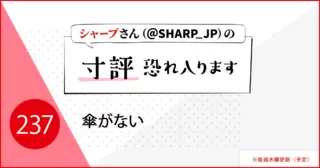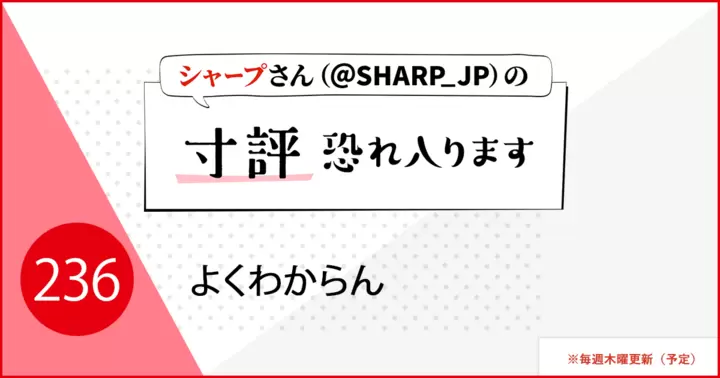
眉間にシワが寄ります、@SHARP_JP です。見た方は「よくわからん」と呻くしか仕様がない作品がある。映画でもマンガでも小説でも音楽でも、それを鑑賞したあとの気持ちが「よくわからん」としか言いようがなくて、それ以上を語るのが難しい時である。どちらかというと、マイナスの評だろう。そして「よくわからん」と思った作品を、私たちは難解とか前衛とか芸術といったタグをつけて、脳内にそっと仕分ける。その後、もう一度それを取り出す、ということはほとんどない。
しかしよく考えれば「よくわからん」は、そもそも賛否のどちらかにひもづく評ではない。正確に言うと「よくわからん」は、賛否の前にある状態ではないか。いいとか悪いとか、おもしろかったとかつまらなかったとか、好きだったとか嫌いだったとか、そう断ずるには尚早で、とにかくいったん判断を留保したいという感情が、われわれが呻く「よくわからん」の本来の姿だろう。
それをマイナスの意味合いで使う人は、鑑賞中に判断をつけることができなかった、良し悪しを宙吊りの状態にされた自分の時間を、どこか「損した」ととらえているのかもしれない。たしかに、足場が不安定な場所に長時間いなければいけないストレスを考えれば、それも無理ないことに思えてくる。
しかし私は「よくわからん」は、けっこう好ましい状態だと考える。なぜなら「よくわからん」はあくまで暫定状態であって、いずれ「よくわかる」かもしれない、未来の可能性に開かれているからだ。ぼんやりした私は、そういう間延びした考えで、保留をわくわくする状態と解釈する。口に入れた瞬間にうまいまずいを判定する味覚ですら、いつのまにかキライな食べ物が好物になったりするのだ。いま下した自分の判断も、案外当てにならないものだろう。
私たちに「いずれわかるかもしれない」という種類の摂取の仕方があることは、とても希望がある。私はそう思っている。だけどしばしば「よくわからんかった」が大量に駆け巡るSNSを見ていると、のんびり構えているのは私だけだろうかと、不安になることもある。
マイハマ兄弟(kabeee 著)
たまにはみなさんも、難解とか前衛とか芸術といったタグをつけた脳内フォルダを見返してみたらいいと思うが、「よくわからん」は必ずしも、むちゃくちゃな作品なわけではない。ただ、むちゃくちゃを目指しただけでは作品にならないのは、他人が見た支離滅裂な夢の話ほど、つまらない話もないことからわかると思う。よくわからんと呻いてしまうモノには、やっぱり今の自分には言い知れない、なんらかの強度があるのだ。
その強度が、必ずしも作者の意図したものなのか、あるいは無意識下に達成されたものなのか、いまいちよくわからなかったりするのがまた、表現とは奥行きのある複雑な行為なのだと思う。このマンガを読んだ人は、同じような感覚を抱くのではないか。なにが「よくわからん」のか焦点を結ばないまま、言い知れぬ不思議な魅力だけを動力に、先へ先へと読み進めてしまう。
思えば、神話とか寓話と呼ばれる太古からある物語は、ことごとくよくわからん話に満ちている。子どもが読む絵本にだって、おどろくほどよくわからん話がある。長らく、難解とか前衛とか芸術といったタグがつけられた音楽を愛好したり志たりしていた私は、よくわかった後にこそ、よくわからんの豊穣な地平が広がっていることをかすかに知っている。ただそこに行くには、宙吊りの時間を手なずける、手間も時間も根気も必要なのが、圧倒的に時間が足りない私たちにとってやっかいなのだろう。私たちは忙しすぎて、じっくりと「よくわからん」に対峙できなくなったのかもしれない。