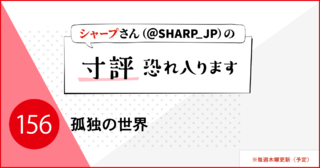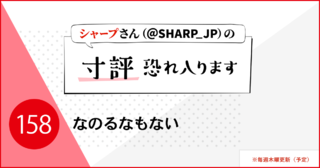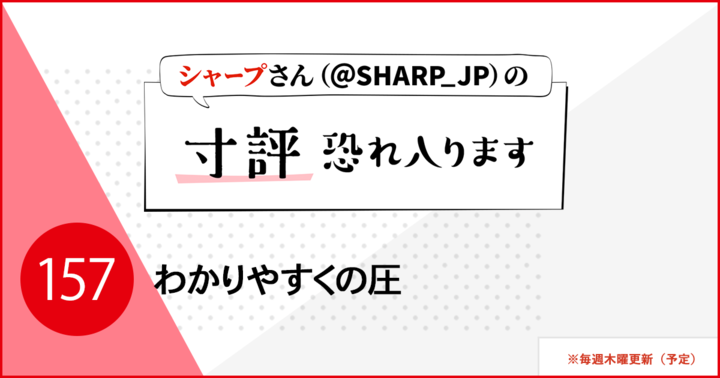
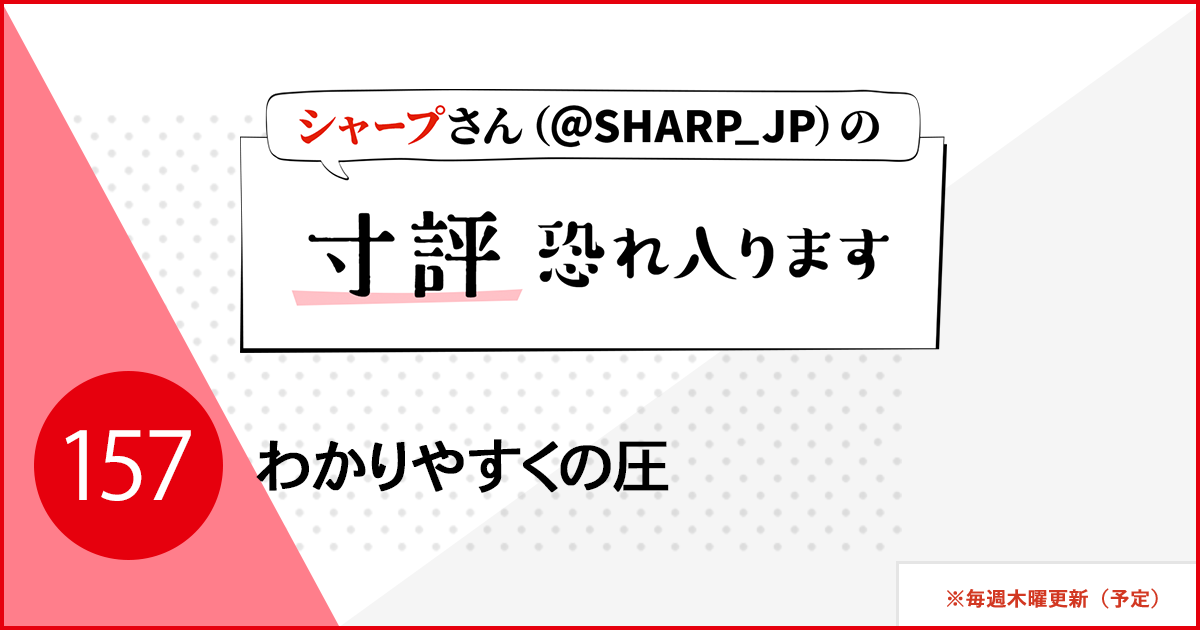
コツコツ働いています、@SHARP_JPです。「××をわかりやすく伝えてください」仕事柄よく言われる言葉である。××には製品や技術とか機能の名称が入る。てい良くお願いされているが、つまりはそれがたくさん売れるようなアイデアやキャッチコピーを考えろ、もしくはツイートをしろというオーダーである。圧ともいう。
言葉を尽くす時間もスペースもないのが広告という場所なので、伝えたいコトを圧縮し、言い換え、取捨選択することはぜったいに必要だ。だからこそ頭を悩ますのだけれど、どれもこれもだれもかれも「わかりやすく伝えてください」と判をついたようにぶん投げられると「あんたはわかりにくいままで売れると思ってたのか」と嫌味のひとつも言いたくなる。
特に家電やスマホは「1台でアレもコレもできる」ことがアイデンティティだったりするので、アレとコレひとつひとつはわかりやすくとも、アレもコレもソレもとパッチワークされると途端に「何が言いたいのかよくわからない」事態が出来してしまう。
家電に限らず、たいていの工業製品やサービスは多くの人の手と知恵を経て作られるのだから、世に出る頃には膨大なこだわりと目論見が付加されて、ちょっとなに言ってるかわからない、となるのもありがちなことなのだろう。よかれと思って家を建て増ししていたら聳え立つ塔ができてしまったので、全貌が見えるミニチュアを作る必要が生じたなんて皮肉なことだが、私の仕事はそのミニチュア作りに通じるものがある。
一方で「わかりやすく」という言葉も信用ならない。たとえば、伝えるコトを減らすのは、わかりやすくなるのに必要だけど十分条件ではない。また多くの人が誤解していることだが、「わかりやすく」は平易な言葉を使えば達成されるものでもない。「わかりやすく伝える」とは専門用語や難解な語彙を避け、子どもでもわかるように書けばいいと考えがちだが、そこがわかりやすさの落とし穴なのだ。
そもそも子どもでもわかるように書けばいいのなら、わかりやすく伝えてとオーダーするあなたでも書けるはずなのだ。かつて子どもだった大人なんだし。むしろ大人が考えるべきは、子どもでもわかるような子どもじみた語りかけをされた大人はどう思うか、ということではないのか。子どもじみた言葉を浴びせられ続けると、人はいつしか子ども扱いされた気分に陥る。バカにされたとさえ思うかもしれない。それはひっくり返せば、子どもじみた言葉ばかりを語る企業や製品は、お客さんはしょせん子どもだと前提している空気が醸し出されるだろう。もし赤の他人から勝手に子どもだと認定されたら、大人はどういう気持ちになるかは考えずとも自明だと思う。
だから「わかりやすく」というのは案外難しいのだ。伝えたい相手に向かって、対等な大人だという信任を足がかりに、それでもなお伝わりにくい言葉を想像し、同時に言葉を伐採していくこと。そのギリギリの均衡に勇気をもって踏み出せるかが、わかりやすく伝えるための必要十分条件だと、私は密かに信じている。
読書して内容を伝えようとするもうまくいかない人(asaborake 著)
繰り返しになるが、私は職業上の要請もあり、わかりやすく伝えるということに過敏である。だからこのマンガを読んで、必要以上に感銘を受けてしまった。ここでは「内容を伝えようとするもうまくいかない人」と自虐的なタイトルがつけられている。が、内容を伝えようとするもうまくいかない人が四苦八苦する様子をマンガにすることで、見事に内容がわかりやすく伝えられている。
ある本を読み、その本を推したい人が、テーブルを挟んだ友人ふたりに本の内容を語ろうとする。だがおずおずした説明にはしょっちゅう友人による茶々入れや脱線、話の腰折れが挟まれる。そここそがうまく伝わっていないポイントなのだが、読むわれわれはそのうまく伝わらない友人の姿によって、わかりにくさの解説になっているのだ。だからマンガの向こう側にいる私たちには、するする伝わってしまう。この構造は発明なのではとさえ、思ってしまった。そして私もついさっき、その本をポチったのだ。
これほど真の目的を達成した仕事があるだろうか。見習いたいものである。