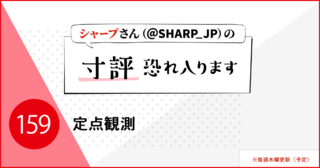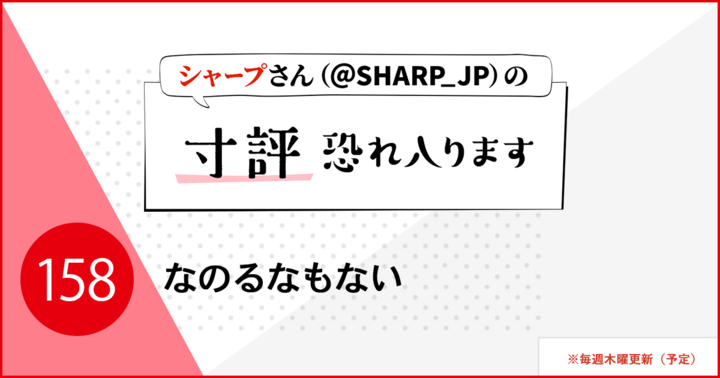
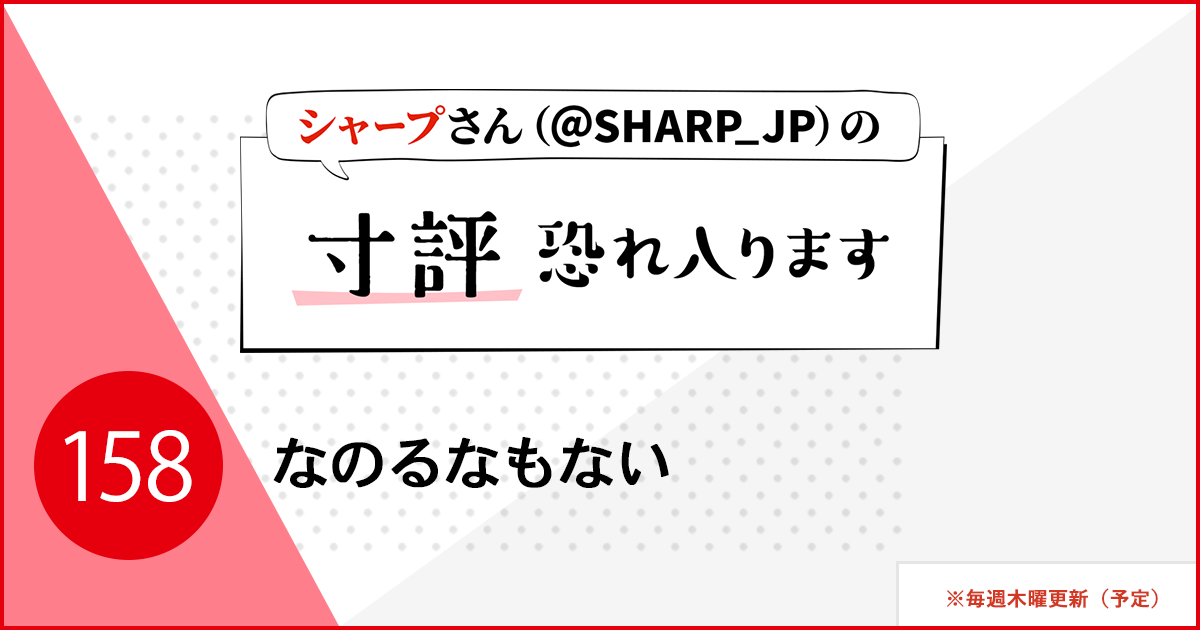
名乗るほどでもございません、@SHARP_JPです。名字がごくありふれた人にはわかってもらえると思うのだが、たとえば病院の待合なんかで名前が呼ばれると、まずは「別の人なのでは」と感じてしまうのである。自分の苗字が耳に入ってきても、自分が呼ばれたと考えるよりも先に、別の人が「はい」と返事をするに違いないと思うせいで、いつも「待って」しまうのだ。
だから私の場合、呼びかけから不自然な間が空いてしまい、待合室が変な静寂に包まれることがしばしばある。静まりかえってようやく私は、そうか私のことかと理解するのだ。呼ばれるのを心待ちにしていたのは私のほうなのに、呼ばれた時に心ここにあらずで申し訳ない。
私の名はありふれている。とくに名字は、ありふれたランキングで上位3つに入るはずだ。高齢化と人口減少が進む国だから、そのランキングも一生不動だろう。現に私はこれまで、学校のクラスで自分の名字を独占できたことはついぞなかったし、いま所属する会社の部門なんて、比較的小さな所帯であるにも関わらず3人も同じ名字の人がいる。とにかくどんな空間にいようが、そこでは私以外に私と同じ名の人がいるという感覚が染みついているのだ。
名前とは本来「あなたは他ならぬあなただ」という事実を示すものだろう。もちろん私たちの名前は姓と名を組み合わせてオリジナルとなり、アイデンティティとして機能するのだが、大人になるにつれて下の名前で呼ばれる場所や機会は減っていく。人は歳をとるにつれ、名実ともに自己を確立していくものだが、ごくありふれた名字の人は、年齢に反比例してだんだん匿名性をまとっていくのかもしれない。
とはいえ、私はありふれた名前ゆえの匿名性にうんざりしているかというとそうでもない。自分が何者でもないイラつきを抱えた思春期ならば、アイデンティティとして機能しない自らの名前に不満も募るだろうが、いまはむしろありふれた名前に清々しささえ感じている。それはどこか、匿名で発言を許されたSNSの空気にも通じる。
もしあなたが他人と被らない個性あふれる名前を持つならば、空っぽのアイコンで人目を気にせずツイートしてみてほしい。その時に感じる風通しの良さと後ろめたさが、ありふれた名前の人が自分の名前に抱いている感覚に近いと思う。
告白した人の様子が変だった。(貝原漱祉 著)
このマンガの本筋やおもしろさとまったく関わりがなくて心苦しいのだが、私はこのマンガを読んだ時、冒頭をくすりと笑う人と、あるあるとうなずく人に分かれるのではないかと思ったのだ。もちろん私は後者である。たぶん私も、目の前で名字を呼ばれて告白されたとしても「オレのことではない」とキョトンとしてしまうのだろう。そして妙な静寂の後、自分勝手な匿名性に慣れきった私は作中の吉田くんと同じく、これはドッキリにちがいないと疑心暗鬼に陥ると思う。
それほど名前とは、深く自己の形成に関わるのだ。だから結婚して姓が変わる人は、また別種の混乱が自己の中に大きく渦巻くのではないかなどと考えるのだが、これはこれで長くなりそうなので別の機会に。