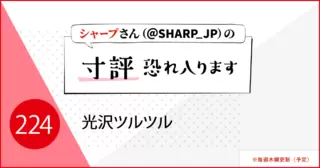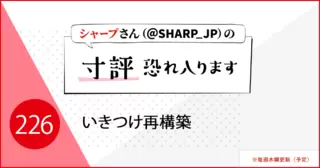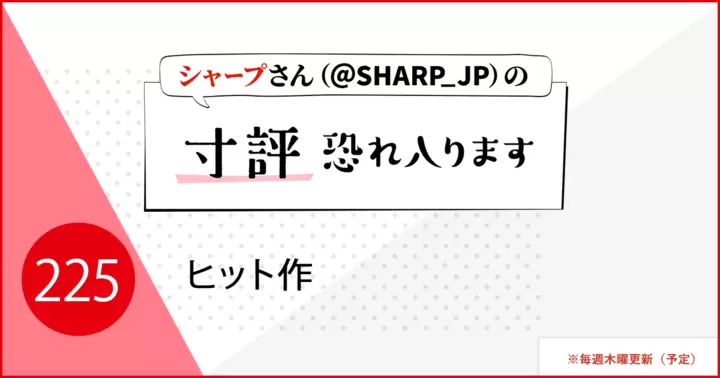
ナナメから失礼します、@SHARP_JP です。いまもその傾向があるにはあるのだが、とくに昔は「みんなが見たり聞いたりしているモノを、自分はあえて見たり聞いたりしなくともよい」と思っていた。素晴らしいモノが世界にあり、それを多くの人がすでに素晴らしいと賞賛しているのなら、いまさら私が賞賛する必要もないし、その暇があるなら、私は誰にも知られていない素晴らしいモノを鑑賞して賞賛すべきではないか、と考えていたのである。
言ってしまえば、私は斜に構えていたわけであり、斜に構えがちな年頃あるいは時代特有の、若気の至りというものであった。当たり前だが、たくさんの人が見ているモノを見ていないからといって、そこに見ていない人の個性が立ち上がるわけではない。立ち上がるとしたら、なんだか偏屈な人間がいるぞとか、どうも話が盛り上がらないヤツだなといった、むしろ没個性な方向の印象だろう。
ただしいまだに「たくさんの人が見ている」と聞くと、どこかの誰かや企業から「たくさんの人が見ているからお前も見ろ」と仕向けられているような警戒心が持ち上がってくる。とりわけ友人知人ではなく、メディアからニュースとしてそれを聞くと、猜疑心はより高まるのかもしれない。非人格的な形で「みんな見ているんだから」と伝わると、かつて私の中にあったナナメに構える心が、ほんの少しこわばるのだろう。自分の行動原理に「たくさんの人がそうしているから」はないんだという、微かな意地がいまも私の中にあるのかもしれない。
マンガ日記 流行について(カゲワサビ 著)
私は漫画を描く人間ではもちろんないけど、このマンガ冒頭で指摘される「君たち流行に乗ることをダサいと思っているだろう」には、ドキリとさせられた。かつて私の中にいた、ナナメに構える私がギクリとしたのだろう。
これもまた当たり前だが、たくさんの人が見たり聞いたりして、そしていいと言っているからといって、その作品やモノの素晴らしさが毀損されるわけではない。素直に考えれば、多くの人の心を動かしているという点だけでもう、その素晴らしさは推して知るべしなのだ。古典や名作と呼ばれるモノはそうやって残り続けてきたし、いまわれわれが生きる現代で次々に生まれる、大ヒットと呼ばれるモノだって、どうして多くの人が夢中になるか、一見あるいは一聴すればわかるだろう。みんながいいと言うには理由がある。みんながいいと言うモノは、どこかしらやっぱりいい。
とはいえ、今と昔では様相がまったく異なるところもある。「たくさんの人が見ている」が膨大という言葉では追いつかないほど、われわれの身の回りにあふれにあふれているのだ。有名か無名かを問わず、SNSのアルゴリズムは世界で刻々と起こる「たくさんの人が見ている」を表示してくる。スマホを手にする私たちは、友人から機械から絶え間なくおすすめされ続けているのだ。
それを消化していけば、私たちの一日はあっという間に終ってしまう。隙間時間すらなくなる。そういう毎日では「なにをどれだけどう見るか」という態度こそを、私たちは問われているのかもしれない。
われわれは見たり聞いたりするだけですら、圧倒的に時間が足らない。素晴らしいモノを素晴らしいと確かめるだけなのに、時間がない。われわれは、流行っているモノをお試ししてみることすら、圧倒的に難しいのだ。素晴らしいモノがあふれる世界にあって、作る側にも享受する側にも、それはなかなか過酷なことではないか。